―-フロイト・セミナー応用篇――
「記憶と意識の相互排他性」について
重元寛人
みなさん、おひさしぶりです。今回からはじまるセミナーの新しいシリーズでは、フロイトの著作をヒントに「意識」の本質にどこまでせまれるかという非常に大それた試みをしたいと思います。フロイトというと「無意識」のことを研究したことで有名ですが、その対極にある「意識」についても深い考察をめぐらしています。彼自身は控えめな言い方をしていますが、実はこの謎に対してかなり真実に近いところまで迫っていたのではないでしょうか。そのヒントとなるのが、メタ・サイコロジー著作の中で何度か提示されている「記憶と意識の相互排他性」という命題です[1]。これは、メタ・サイコロジーの局所論的な視点において、記憶と意識は互いに別のシステムにおいて生じるという言及であり、さらに「意識は記憶の痕跡の代わりに発生する」というように記憶が意識の本質を規定するということを示唆する命題なのです。詳しいことは順に説明していきますが、本論に入る前にいくつか前置きをしておきましょう。
まずは「意識とはなにか」という問いそのものついて吟味してみます。フロイトが晩年に分析理論の最終形態として記そうとした未完の著作『精神分析概説』に次のような記述があります[2]。
この研究の出発点は、あらゆる説明と記述を許そうとしない意識という究極的な事実である。
40年あまりにわたって心の問題を追及し続けたフロイトにして、意識はこれほどにとらえどころがないものだということでしょう。きちんとした記述や説明ができないにもかかわらず、われわれにとって自分自身に意識があるということは、他のあらゆる事よりも確実な真実です[3]。そして、精神分析学をはじめとして人間の主観を扱う学問すべては、このパラドックスを出発点にせざるをえません。同様の趣旨の記述として、1915年の『無意識』に次のような一節があります[4]。
意識はわれわれに、ただ自分の精神状態を伝えるにすぎない。他の人間もまた意識をもっているということは、われわれが他人の行動を理解するために、われわれの知覚できるその人の表現と行為をもととして、類推できうる一つの推論である。
ここで言わんとしていることはよくわかります。しかし、「意識がわれわれに自分の精神状態を伝える」という時の「われわれ」とか「自分」というのはなんでしょうか。意識とは別に「わたし」といった主体あるいは主観の存在を前提にしてもよいのであれば意識の記述は可能ですが、それは問題を他に移し変えたに過ぎません[5]。この文は「みんな自分に意識があることはわかっていますね」と直感的な同意を求めている以上のことは何も述べていないのです。その次の文(「他の人間も‥‥」)も、他人の意識を類推することしかできないということによってやはり意識の記述不可能性を示しているわけです。
この問題をこれ以上追及すると哲学的な深みにはまってしまいそうです。ここでは単に「(われわれが知りたいと思っている)意識とは定義不可能なものである」ということを確認しておくにとどめます[6]。「定義不可能なものについて知ることは最初から不可能である」と言うとここで話をおしまいになってしまうのですが、今回は別の側面からの攻略を試みようと思うのです。すなわち「記憶」という比較的記述も説明もしやすそうな現象の考察を通じて、「意識」という不可思議なものの本質を浮かび上がらせようというのが本論の目的であります[7]。
もうひとつの前置きとして、フロイトの学問的姿勢について述べておきます。周知のとおり彼はもともと神経組織学・生理学の研究者であり、生物学的視点から科学的心理学を構築するという野心的な試みをしました。さすがのフロイトも当時の生物学的知識によってこの試みを完成させることはできず、その後は精神分析学によって心理学理論を構築することに専心します。そうしてできたメタ・サイコロジーを読んでみますと、内容面で初期の試みと重なるところが多いですし、記述の随所に客観的視点を尊重する自然科学の姿勢があらわれています。フロイトの学問的姿勢にはこのような二重性が内包されており、そのために双方のグループからの批判にさらされてきたところもありました[8]。ですが、脳科学の領域において意識の生物学的基盤についてさかんに議論されるようになった今日、フロイトの思考の歩みについて、その生物学的志向も含めて再検討することは大変有意義なことと思われます。
それでは本論に入りましょう。まずは1896年にフロイトが友人フリースに宛てた手紙の中で構想したいわゆる『科学的心理学草稿』[9]について、今回のテーマに関連する部分を要約して紹介します。これは、人間の心理現象をニューロンが形成するネットワークの働きとして記述する試みです。
神経の基本単位となるニューロン[10]は、量と周期という2つの特性を持つ興奮を、その細胞体に蓄えたり、軸索を通じて放出して、他のニューロンに伝えたりする。それぞれのニューロンは自ら保持する興奮の量(Qη´)を放出してできるだけ少なくしようとする傾向を持つ。これを、ニューロン惰性の原理と呼ぶ。
ニューロンには3種類ある。
φ(ファイ)ニューロンは、外界からの刺激をニューロン・システム全体に伝える働きをする。その際、外界の大きな刺激量は、ニューロンの扱える小さな量(Qη´)に変換される。また、周期については、φニューロンごとに特定の周期の刺激のみを抽出して伝導する。φニューロン自らは、受けとった興奮を保持せずすぐに他のニューロンに伝えてしまうので、透過性ニューロンとも呼ばれる。
これに対して、ψ(プサイ)ニューロンは非透過性であり、受けとった興奮を自ら保持する。このように、興奮を与えられることを「備給」という。備給された興奮の量(Qη´)は可変であり、周期は一定である。ψニューロン同士は接触防壁を介して結びついており、興奮が行き来するためにはある種の抵抗を乗り越えねばならない。ψニューロンのこのような性質が、記憶ということを可能にする。ψニューロンの間にある接触防壁の疎通は、興奮の通過によって変化する。記憶は、ψニューロン間の疎通の差異によって表現される。例えば、ニューロンaに備給された興奮が、ニューロンbとニューロンcのどちらへ転換されやすいか、換言すればニューロンaがニューロンbとニューロンcのどちらにより強く連合(連想)[11]しているかということが、記憶の根本原理となる。ψニューロンによって構築されたψシステムは記憶のためのシステムである。
ω(オメガ)ニューロン(知覚ニューロン)は、ごくわずかな量(Qη´)と、多様な周期を受け入れる能力を持つ。ωニューロンは知覚のためのシステムすなわちWシステムを構築する。ψシステムから一定の備給を受けた状態で、外界からφニューロンとψニューロンを介して伝達された興奮の周期がWシステムにおいてψの保持する固有周期から逸脱することによって、知覚の質(Qualitat)すなわち意識的感覚が生じる。快・不快の感覚もWシステムにおいて生じる。ψシステム全体の量の増大はWシステムの備給状態に影響を与えることによって不快の感覚を生じさせ、ψシステムにおける量の減少は快の感覚を生じさせる。
備給・転移・連合(連想)・投影・快不快原則など、その後のフロイト理論の基礎概念がすでにここに登場しています。記憶がニューロンどうしの連合によって成立するという考えかたや、意識が知覚にともなう質に関係するといった見方は、そのまま現代の脳科学にもってきても通用しそうなほど示唆に富むものといえましょう。
今回のテーマである記憶と意識の問題についてはどうでしょうか。記憶はψシステムの連合によって成り立ち、そこには意識は関与しません。一方意識的感覚は知覚の質としてWシステムにおいて生じるのですが、そこでは記憶のような持続的な変化はおこりません。このように記憶と意識は別のシステムの働きにより生じるという意味で「相互排他的」といえます。もっともそれは、それぞれが独立に、無関係になりたつということではありません。これから先でもみていくように、意識の様相は記憶をつかさどるψシステムの動向に影響され規定されます。
『科学的心理学草稿』は、あくまでも草稿であってフロイト自身の意図で出版にいたったわけではありません。彼によって最初の体系的心理学が公にされるのは3年後の『夢判断』[12]になります。その第7章「夢事象の心理学」では、「心的局在性」という考え方を基礎に心的装置についてのモデルが提示されました。心的局在性とは解剖学的概念とは関係のない比喩的な概念ということですが、モデルの内容をみるとニューロンから心的装置を描写しようとした『草稿』を下敷きにしていることがわかります[13]。心的装置は、図に示すように望遠鏡に似た組み立て道具に例えられました[14]。
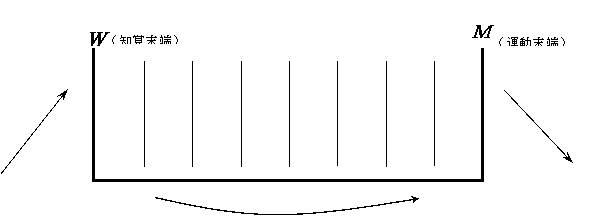 |
心的装置に外部から到達した刺激は、図の左端にある知覚末端を興奮させ、その興奮は次々にその右隣にあるψシステムあるいは記憶システムに伝達され、最終的に運動末端から放出されます。記憶システムにおいては、通過する興奮によって記憶痕跡が残されます。それは、知覚からの印象が、同時性の連合とか、言語表象との連合とか、いろいろな観点から多重的に定着される過程です。しかし、知覚末端(W)自体は、常に新たな興奮を受け取れるように、持続的な痕跡を残しません。すなわち、知覚(W)システムは記憶力を持ちません。
この図式を意識との関係から見ると、ψシステムのほとんどは決して意識されることのない、無意識システムです。運動末端近くのいくらかが、前意識システムであり、注意を向けられることで意識化可能です。意識はシステムとしては、この図に位置づけられません。
以上をふまえ、『夢判断』第7章で問題の「記憶と意識の相互排他性」ということに言及している部分をみてみましょう[15]。
変化を保存する能力を持たない、つまり記憶力をもたないWシステムは、われわれの意識にとっては、種々雑多の感性的質を提示する。ところが逆に、もっとも深く刻みつけられたものも含めての、われわれの記憶は、本来無意識である。むろんそれらは意識化されうる。しかし記憶されているものが無意識状態のうちにいろいろの作用を行うということには疑いを容れない。われわれがわれわれの性格と呼ぶところのものは、いうまでもなくわれわれが内外界から受けた諸心象の記憶痕跡の上に成り立っている。しかもまさに、われわれにもっとも深刻にはたらきかけた諸印象は、われわれの幼少期のそれであり、ほとんど絶対に意識化されることのないそれである。しかし無意識になっている記憶がふたたび意識化されると、それは諸知覚に比してきわめて微弱な質を示すか、あるいは感性的な質をまったく示さないかの、いずれかである。そこでもし、記憶と記憶に伴う質とがψシステムにおいて意識に対して相互排他的だということが実証されるならば、神経興奮の諸条件への、将来有望な洞察の道が開けることであろう。
いよいよ本論のメイン・テーマである「記憶と意識の相互排他性」ということが登場しました。引用の最後の方は難解ですが、わかりやすいところから確認していきましょう。
第一に知覚のためのWシステムは記憶力をもたないということ。例えばものを見るときに感覚器官である眼は見たものを記憶したりしないのは当然のことです。「目に焼き付ける」というのは比喩的な表現であって、字義どおりにそうなったら次に何かを見るときに邪魔になってしかたないでしょう。同様な理由から、心的装置において見たものを認知するWシステムもやはりそれ自体記憶力をもたないと考えられます。要するに記憶というのはある種の容量を必要とするので、新たな刺激を受け入れるシステムにはふさわしくないということでしょう。
第二にそのWシステムが、意識に対して種々雑多な感性的質を提示するということ。意識の本質は知覚の質であるという『科学的心理学草稿』の考え方を受け継いでいます。また、後でみていくように後期理論ではWシステムは意識のシステムと統合され知覚―意識(W-Bw)システムとなります。
第三に記憶が本来無意識であるということ。ここは大事なところです。常識からすると、はっきりと意識した事柄のほうがしっかりと記憶に残り細かいところまで思い出せます。そう考えると、記憶は本来意識的なのではないかとも思えます。そう思えるひとつの要因は「記憶」ということのとらえ方、定義の問題にあります。一般に、記憶とは何かを覚えて(記銘)それを一定期間以上保った後に再生する一連の過程のことをいいます。この過程のうちの再生を「思い出すこと」ととらえると、記憶は意識的であると考えたくなります。しかし、記憶の再生は思い出すことばかりではありません。本人は思い出しているつもりはなくても過去の記憶がその行動パターンに影響をおよぼしていることもあるのです。例えば、自宅から駅に行くのにいつもわざわざ遠回りをする人がいて、彼自身はその理由をはっきり答えられないが実は幼少期に犬にかまれた場所を避けているといったような場合です。しかもこれは例外的なケースというわけではなく、むしろこちらのほうが記憶の本来のかたちである、というのがフロイトのとらえ方だと思います。とくにわれわれが幼少期に記憶した印象というものは、自分自身では意識しないかたちで行動パターンに大きな影響をおよぼしているわけです[16]。
まとめるとこうなります。意識はWシステムから知覚の質をうけとるが、そのWシステムは記憶能力をもたない。一方記憶は本来無意識である。これが「記憶と意識の相互排他性」という命題が意味するところの半分です。
つづいて後期構造理論をみていきましょう。意識について述べた『快感原則の彼岸』からの引用です[17]。
意識は本質的に、外界からくる興奮の知覚と、心的装置の内部だけから発生する快と不快の感晴を供給するものであり、知覚―意識(W-Bw)システムには、一つの空間的な位置を定めることができる。(中略)他の心的なシステムとは異なり、意識(Bw)システムには意識における興奮プロセスが、システムの要素の持続的な変化の痕跡を残さず、意識化の現象の中でいわぱ消減してしまうという特別な性質があることになる。
『夢判断』と同様のことですが、新たな記述もあります。ひとつは知覚と意識が、知覚―意識(W−Bw)システムとして統合されたシステムの働きとされたこと。そしてさらに重要なことは、意識化という現象の中で、興奮が持続的な痕跡として残されずに(すなわち記憶されずに)消滅してしまうという言及です。消滅させることにこそ意識の本質があると示唆しているようにも受けとれます。
知覚−意識システムについては、さらに踏み込んだ記述が1925年の小論『マジック・メモについてのノート』にあります[18]。
これまで自分の胸にしまってきたこの仮説では、備給の刺激伝達が自我の内部から、完全に透過性の知覚―意識(W-Bw)システムへと、急速で定期的なインパルスとして送り出され、撤回される。このシステムがこのような方法で備給される限り、これは意識に伴う知覚を受け取り、無意識の記憶システムに興奮を伝達する。備給が撤回されると同時に、意識の<灯>が消え、このシステムの機能は停止する。無意識が、知覚―意識(W-Bw)システムを介して、外界に触手を伸ばし、外部の刺激を試食すると、急いで触手をひっ込めるかのようである。
知覚というものが思いのほか能動的なプロセスであるということが述べられています。知覚とは、過去の様々な記憶像から外界についての予想をし、刺激をむかえにいく過程であると考えるとわかりやすいでしょう。では、このような能動性はどこからくるのでしょうか。
ここでもう一度『夢判断』のモデルにもどって検討します。図式で示された心的装置は一見受動的な反応機械のようですが、そこに心の原動力たる「願望」という概念が加わると俄然ダイナミックな様相が出てきます。願望とは、かつて欲求充足に結びついた知覚と同じものの再出現をめざす営みです。つまり何かを見たい、聞きたい、感じたいということです。例えばかつて空腹の苦痛を癒してくれた母親についての知覚が、後の苦痛な状況で願望の対象になるのです。ポイントは、願望が最終的にめざしているのが、運動(行動)ではなく、知覚であるということです。運動をめざしている(なにかをしたい)ように見えるときにも、実は運動の結果えられる知覚が目的なのです。
ここから、退行という概念がでてきます。退行とは、心的装置において、興奮が通常とは逆に、運動末端から知覚末端の方に移動していくことです。夢や幻覚などの完全な退行においては、外部からの刺激によるのではなく、主に内的な願望をみたすかたちで知覚が出現します。例えば「誰か特定の人に会いたい」という願望は、その人の顔を見て声を聞きたいということです。通常この願望を充足させるためには、その人に会いに行くという行動をとらねばなりません。しかし夢や願望においては、そのような手続きなしにその人の顔を見て声を聞くことができるというわけです。
つまり心的装置において通常刺激は知覚末端から運動末端の方向に進んでいくけれど、それはなんの抵抗もなしに流れているわけではなく、むしろ退行という逆方向への傾向との相克がつねにあるということです。夢や幻覚は退行の極端な例ですが、通常の生活で私たちがありのままにものを見ているように思える時でも、外からの刺激を純粋に受け入れているわけではなく、ある種の期待をもって見たいものを見ているということなのかもしれません。
中期以降のメタ・サイコロジーでは願望という概念はあまり使われなくなり、かわって「欲動」が心的装置の原動力になります。そして、後期理論では、この欲動についての最も根源的な性質が明らかにされました。
フロイトは、『快感原則の彼岸』において、外傷神経症者の夢、1歳半の小児の糸巻き遊び、陰性治療反応、そして同じパターンの運命を繰り返す人物について分析を行い、そこに外傷体験を反復しようとする強い傾向を発見し、「反復強迫」と名づけました。これは大変逆説的な話です。人間であれ他の動物であれ快を求め不快を避けようとする基本的な性質があるということは納得できます。そのような快感原則からすれば、外傷体験の記憶というのはなるべく早くに消し去る方が理にかなっているでしょう。ところが、現実にはそういう不愉快な記憶にかぎっていつまでも残り、悪夢とか、自滅的な行動とか、神経症症状とか、さまざまな形でしつこく本人を悩ませるのです。反復強迫は、従来の快感原則と矛盾する上、それは単なる例外ではなく欲動の基本的な性格であることが明らかにされました。こうして有機体を支配するもっとも根源的な原理として涅槃原則が提示されたのです[19]。
外傷体験の反復という考え方は、フロイトの不安理論にも大きな変更をもたらします[20]。それまで不安は抑圧の結果生じると考えられていましたが、新しい理論によると不安は自我に危険を知らせる信号であり、この信号をもとに自我は抑圧や他の防衛を行います。
不安の前提条件は幼少期の外傷体験により作られます。外傷とは、未熟な心的装置に到来した強すぎる興奮によって刺激保護が破綻することです。この過程によって未熟な心的装置は、原抑圧という決定的な方向づけをなされるのです。重要なことは、人間においてこの種の外傷体験は避けることのできない運命であるということです。人間の赤ん坊はあまりにも未熟な状態で生まれてくるので、養育者の助けなくしては1日も生きることができません。空腹やあらゆる生命の危機的状況に襲われたとき、生まれたての赤ちゃんはただひたすら泣き叫ぶしかないのです。この外傷体験が母との分離不安、そしてその裏返しとしてのしがみつくような愛着のもととなり、エディプス・コンプレクスの基盤を形成するというわけです。
知覚における能動性は、ものの存在を期待するということです。その背後には、対象を失うことへの不安、対象の存在を強迫的に確認しようとする傾向があるのかもしれません。
さて、ここまでくると幼少期の外傷体験ということは単なる個人的な記憶といった枠内にはおさまらない問題であるということがわかります。それはすべての人間にとって避けられないことであり、ヒトという種に普遍的な運命であるからです。
そこで、歴史的考察が必要になります。フロイトが最晩年に記した著作『モーセと一神教』に次の記載があります[21]。
われわれは長いあいだ、先祖によって体験された事柄に関する記憶痕跡の遺伝という事態は、直接的な伝達や実例による教育の影響がなくても、疑問の余地なく起こっているかのように見なしてきたと告白しなければならない。
このような記述をもとに、フロイトが獲得形質の遺伝という誤った主張をしていたと批判をする人がいます。確かに、現代の遺伝学では個人の獲得した形質や記憶が直接遺伝することは否定されています。しかし、それでも「記憶痕跡の遺伝」ということは成立し得ます[22]。ある環境において生きる個体群の中から、その環境により適応的に行動するパターンを身につけているものが、より多くの遺伝子を次世代に伝えていくことで、種としての行動パターンは進化します。この過程はまさに、その時代時代の環境と行動パターンをDNAに刻み込んで「記憶」させていく過程ともいえましょう。
話は進化という壮大な問題に到達しました。フロイトはダーウィンを愛読し、著作の中でも何度も引用しています[23]。次回のセミナーではこの話題を追及することで、意識の本質にさらに迫っていきたいと思います。