――フロイト・セミナー応用篇――
第2回 フロイトに学ぶ記憶と意識の進化論
重元寛人
前回のセミナーでは、フロイトが提示した「記憶と意識の相互排他性」という命題について『科学的心理学草稿(1896)』、『夢判断(1900)』、『快感原則の彼岸(1920)』そして『マジック・メモについてのノート(1925)』をとりあげて検討しました。今回は、前回の最後にふれた進化論的考察をさらに追求し、意識の生成について簡単なモデルを作ってみるところまで到達したいと思います。
まずは『快感原則の彼岸』の引用からこれまでの復習しましょう[1]。
絶対に確実というわけではないが、意識化される行為と、記憶の痕跡を残す作用が、同じシステムの中に共存することはできないと考えたくなる。すると、意識(Bw)システムにおいては興奮プロセスが意識化されるが、持続的な痕跡は残さないと考えられる。(中略)意識は記憶の痕跡の代わりに発生するという命題は、少なくとも明確に定式化された命題であるということは認めなければならないだろう。
このように、「記憶と意識の相互排他性」という命題は、単に局所論的観点から記憶と意識の両プロセスが心的装置の別の場所で生じるということだけでなく、「意識は記憶の痕跡の代わりに発生する」というように、意識の本質が記憶との関係から規定されるということを示唆しています。
そこで、記憶というものを追求していけば意識の秘密にせまれるのではないかという話になります。フロイトは「記憶」ということを心的装置に残される痕跡ととらえていました。絶対的なあるいは中心的な主体というものを置かないということはフロイト理論の重要な特徴のひとつだと思いますが[2]、ここにもその姿勢はあらわれています。つまり「痕跡」という言いかたにより、記憶はそれを記録したり思い出したりする主体というものととりあえず切り離して定義されます。物事を自由に記憶したり思い出したりする際の主体性を、われわれ自身(自我)はすべて掌握しているわけではありません。むしろ記憶はわれわれの意識しないところで痕跡を残しますし、後になってそれ自体が自らを再現させることを迫ってくるようなところがあります。つまり、記憶そのものがある種主体的な性質(意思決定の要因)をもっているということです。
精神分析の治療技法と理論を作り出した当初、フロイトは神経症の原因を個人の幼児期における外傷的な記憶に求めていました。しかし、経験を積むにつれて患者の語る外傷体験が必ずしも実際におこった出来事ではなく、空想の産物であることも多いということに気づきました。そのような空想にみられる共通性、普遍性に注目し、エディプス・コンプレクスや去勢コンプレクスの理論が定式化されたことは周知のとおりです。そのような普遍的な空想の根元について、最晩年の著作『モーセと一神教』では次のよう述べられています[3]。
エディプス・コンプレクスや虚勢コンプレクスにおいて神経症の子供がその両親に対してとる態度は、個人的な事件として正当化されるとは思われない。それは、太古の種族の体験へと結びつけることによって、つまり系統発生的に考察して、はじめて理解されるような反応を無数に表している[4]。
もし「個人的な事件」が真に個人的であるならば、それは子供によってそれぞれに異なった体験になり、その結果としてのコンプレクスも多種多様ということになるでしょう。ところが、多くの患者を分析した結果、「母を愛し父に殺意をいだく」といった願望や「ペニスを切り落とされることへの恐怖」というものはよくみられる体験であり、そこから導かれるコンプレクスも多くの人に共通したものであることが明らかになったのです。この普遍性を説明するのには個人の体験という枠内にとどまっていてはもはや困難であり、人間の祖先であった「太古の種族の体験」に結びつけてはじめて理解可能になるというのです。それはどんな体験かといえば‥‥、
人間は、彼らがかつてひとりの原父をもち、そしてその原父を打ち殺してしまったということを──独特のかたちで──常に知っていたのだ、と[5]。
フロイトは、ダーウィンが『人間の起源と性淘汰』の中で提示した原始ホルド仮説[6]にヒントを得て、『トーテムとタブー』でエディプス・コンプレックスについての歴史的解釈を行いました[7]。人類の起源においておこった原父の殺害という歴史的事件が、現代人のエディプス・コンプレックスの基盤を形成しているというのです[8]。
『モーセと一神教』からの引用を続けます[9]。
われわれは長いあいだ、先祖によって体験された事柄に関する記憶痕跡の遺伝という事態は、直接的な伝達や実例による教育の影響がなくても、疑問の余地なく起こっているかのように見なしてきたと告白しなければならない。
(中略)
もしも太古の遺産のなかに後天的に獲得された記憶痕跡が存続していると想定されるならば、個人心理学と集団心理学のあいだの溝に橋が架けられるし、諸民族は個々の神経症者と同じように取り扱われうる。
このような論述から、フロイトはラマルキズム(獲得形質の遺伝という誤った主張)を前提としているという非難を浴び、そのために「太古の遺産」というアイデアもあまりかえりみられることがなかったものと思われます[10]。このあたりの事情については一般に誤解もあるようですので、ここで少し整理をしておきましょう[11]。
ラマルクの展開した進化論では、生物に内在するより複雑で完全なものへと変化していく傾向が強調されました。進化過程においては、個体がある器官をよく使用したりしなかったりすることが、子孫に伝えられ、それらの器官を変化させていくとされました。この考え方を用不用の遺伝あるいは獲得形質の遺伝と呼びます。
ダーウィンは、進化の要因として自然淘汰[12]をもっとも重要視しましたが、獲得形質の遺伝も容認し、その理論の中に取り入れていました。ダーウィンの時代には、遺伝の本質については何も解明されておらず、また生物の進化に要した時間について現在よりもはるかに短く見積もられていたため、自然淘汰のみから生物の複雑な器官が生じたことを説明するのは難しいと思われたのでしょう。ダーウィンがラマルクに対して批判的だったのは、獲得形質の遺伝についてではなく、彼が生物に内在する複雑化への傾向を仮定した点でした[13]。
獲得形質が遺伝しないという現代的な見解を確立するうえで、もっとも影響力のあった人物はアウグスト・ヴァイスマン(1880〜1914)であると言われます。彼は、生物についての細胞レベルでの観察をもとに、個体が獲得した形質や経験には影響を受けずに、不死の「生殖質」が子孫に受け継がれていくことを示しました。その後、1953年にジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが遺伝物質であるデオキシリボ核酸(DNA)の構造を解明し、「遺伝情報はもっぱらDNAからのみ一方的に伝達される」という分子遺伝学におけるセントラル・ドグマが確立され、獲得形質の遺伝はほぼ完全に否定されました。
フロイトは、『快感原則の彼岸』の中でヴァイスマンの考え方を引用し、生の欲動と死の欲動の理論との類似性を指摘しています。ただ、個人の体験の記憶が遺伝されるという考え方には最後までこだわっていたようです。
個人の体験の記憶が直接子孫に伝達されるという考えは間違いであったといわざるをえませんが、それでも「太古の遺産」という概念は成立しうるし、依然として有用な概念と思われます。次は、同じ『モーセと一神教』からの引用です[14]。
動物の本能は、新しい生活状況が昔から慣れ親しんできた状況であるかのように振る舞うことをはじめから動物に許す。この動物の本能生活全般に関して説明が可能であるとするならば、それは、動物がその種の経験を誕生と共に持ち込んできた、すなわち、それらの先祖によって体験されたものごとに関する記憶をおのれの内部に保持し続けていた、と言うしかないだろう。範囲と内容は別のものであっても、動物の本能に対応するのが人間に固有の太古の遺産なのだ。
動物の本能は、自然淘汰による進化の産物です。それは、先祖にあたる個々の動物の体験を直接うけついだものではなく、偶然生じた小さな突然変異が自然淘汰によって積み重ねられたものにすぎません[15]。このような見事な本能を見ると、獲得形質の遺伝を信じたくなるのも無理はありませんが、しかし過去の環境とそれに対する適応的行動を記録するということにかけては、実は自然淘汰の方がはるかに有効なのです[16]。なぜなら獲得形質の遺伝は世代を重ねるにしたがって多くの個体の経験によって薄められてしまうでしょうが、自然淘汰はその時代の環境に適応的なものを選んで蓄積していくからです。「動物がその種の経験を誕生と共に持ち込んできた、すなわち、それらの先祖によって体験されたものごとに関する記憶をおのれの内部に保持し続けていた」という一文は、自然淘汰によってこそ成立することなのです。
自然淘汰のふるいをくぐりぬけて受け継がれたDNAの中には、先祖たちのおかれていた環境とそこでの彼らの行動の記憶が刻み込まれているといってよいでしょう。そして同様の「太古の遺産」は、ヒトもまたその先祖から受け継いできているはずであります。
フロイトの生命観・進化観にはいる前に、ダーウィンの自然淘汰説についていくつかの点を確認しておきましょう。第一に「自然は飛躍しない」ということ。『種の起源』からの引用です[17]。
自然が突然一足とびにまったく違った構造をつくりださないのはなぜなのか。自然淘汰説をとれば、その理由がはっきりわかるはずだ。なぜなら、自然淘汰は連続して生じる軽微な変異をうまく利用してのみ働くからである。自然というのは決していきなり飛躍することなどできず、ゆっくりだが確実に短い歩調で前進するしかないのである。
ここにはダーウィンの進化論のエッセンスがあります。軽微な変異を自然淘汰によって積み重ねていく、というこの単純な原理によって、自然界のすべての動植物がもっている見事なまでの形態、機能、本能が説明できるとは当時はなかなか理解されませんでした。(今でも必ずしもよく理解されていないかもしれません[18]。)その後の遺伝学・地質学・考古学など関連分野および進化生物学自体の発展の中で、ダーウィンのこの基本的な考え方の正しさは確固たるものになってきています。
第二のポイントは、より高度なものになるということは自然淘汰の必然ではないということです。
自然淘汰にしろ最適者生存にしろ、必ずしもより高度なものに発達するという意味ではなく、変異が生じ、その変異が当の生物にとって有利であれば、その変異を利用する方向に作用するにすぎないからだ[19]。
だから、ミミズのように下等な動物にとってより高度な構造をもつようになることが有利でなければいつまでも改良されずに下等なままである、とダーウィンは述べています。ラマルクの進化論とダーウィンのそれとの決定的な違いはこの点です。「進化」という言葉自体が、より高度なものをめざすことのような一般的な意味を含んでいるので誤解を生じやすいのかもしれません。
重要なことは、ある変異が生物にとって有利かどうかということがその生物自体によってではなくその生物がその時におかれている環境によって決まるということです。未来の環境に適合するためにある性質を進化させることはありませんし、完成した時にのみ役に立つ「進化途中の器官」といったものも存在しえません。
自然淘汰の決定因たる環境とは、気候や地形以外は他種の生物との関係によって規定されます。昆虫は鳥などの餌食になりにくいような保護色を改良していくし、鳥は餌の種類に応じて嘴の形を改良していくし、草食獣はセルロースを消化する腸と逃げ足の早さを、肉食獣は巧妙な狩りの方法を改良していくわけです。力が強いとか、走るのが速いとか、知能が高いといったような、一見多くの動物に有利になりそうな性質も、それをもった個体が生存競争において有利となるのでなければ採用されません。不用な性質を持つことは、じゃまになったりエネルギーの無駄になったりすることで、かえって不利となるでしょうから。生物は、そのおかれた環境と生活方法にとって、必要なものを必要なだけ(コストも含めたバランスが最適になるように)身につけていく。自然淘汰はそのように働きます。
フロイトに戻ります。『快感原則の彼岸』で、彼ははじめて生の欲動と死の欲動の対立という考え方を打ちだしました。それまでの理論で対立関係におかれていた自己保存欲動(自我欲動)と性欲動は、生の欲動に統合されました。生の欲動と対立するものとして、死の欲動が登場するのですが、これは非常にわかりにくい概念です。純粋な死の欲動は見えにくく、心の奥底で不気味にうごめいています。2つの欲動は、混合したり分離したりしながら複雑にからみあい、生の欲動の営みにみえる活動の背後に死の欲動が働いていたり‥‥といったことを繰り返したあげく、最終的には死の欲動が勝利をおさめる、というのがどうやらフロイトの結論のようです[20]。
『快感原則の彼岸』では生の欲動と死の欲動の対立を、人間の精神の営みにとどまらず、単細胞生物をふくめたすべての生物にも当てはめ、さらに生命の歴史全体にも適応しようとしています。そこで、ここからは私のアイデアですが、それぞれの欲動に対応する進化の原理を考えてみました。
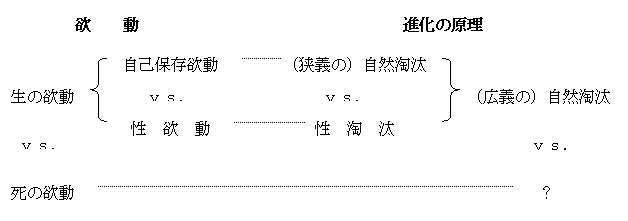
自己保存欲動に対応するのは、狭い意味での自然淘汰です。自然淘汰によって、それぞれの種の生物はよりよく生き残るための本能を進化させてきました。性欲動に対応するのは、ダーウィンが性淘汰と呼んだものです。これは、クジャクの雄が雌に好まれる華やかな模様の羽を進化させたり、鹿の雄が別の雄から雌を戦いとるために大きな角を進化させたりするように、それぞれの性の個体が他方の性の個体との生殖をより有利にすすめる方向へと淘汰されていく過程です。ダーウィンは性淘汰を重視し、とりわけ類人猿からヒトへの進化において大きな役割をしたことを仮定しています[21]。現代の進化生物学では性淘汰を自然淘汰の特殊形とみなしていますから、この両者を合わせたものが広い意味での自然淘汰といえます。
それでは、死の欲動に対応する、この「?」の所にはいるのはなんでしょうか。『快感原則の彼岸』からの引用です[22]。
生命は、発展のすべての迂回路を経ながら、生命体がかつて捨て去った状態に復帰しようと努力しているに違いない。これまでの経験から、すべての生命体が内的な理由から死ぬ、すなわち無機的な状態に還帰するということが、例外のない法則として認められると仮定しよう。すると、すべての生命体の目標は死であると述べることができる。これは、生命のないものが、生命のあるもの以前に存在していたとも表現することができる。
過去のある時点において、現在もなお想像できない力の影響によって、生命のない物質の中に生命の特性が芽生えた。これは後に、生命のある物質の特定の層において意識が発生するプロセスにとって、模範となるものであったのではないだろうか。それまで生命のなかった物質の中で緊張が発生し、この緊張は自己を解消しようとした。このようにして、最初の欲動が生まれた──生命のない状態に帰還しようとする欲動である。
生命というものは、生命のない状態に戻ろうとする。もっと正確に言えば、すべての物質には単純で均一な状態をめざす傾向があり、有機体(生命)も例外ではないということです。個体においても進化過程においても、生物は生命の維持と複雑化を求めているように見えますが、それは最終的に到達する死への迂回路にすぎません。
つまり、自然淘汰による進化と対立し、死の欲動に対応するものは、生命の維持と有機体の複雑化に抵抗し生物を死滅させようとする傾向のことです。それは物質世界全体を支配する均質化への傾向であり、エントロピーの法則と言ってもいいのかもしれません。自然淘汰によりもたらされる生命の発展と複雑化ということは、均質化への傾向に抵抗する形でなされており、その結果として個々の生物はますます高度の緊張を強いられることになるというわけです。
比喩的な言い方ですが、自然淘汰ということは、その渦中にいる個体にとってはさぞかし苦痛なことでしょう。食物の不足や外敵からの脅威の中で、欲求に突き動かされ、苦痛から遁走し、他の個体との闘争を繰り返したあげく、勝利者も敗北者もいずれは死んでしまうわけです。自然界をみると、そこにいる動植物の見事な形態や機能、そしてそれらが織りなすドラマを賞賛せずにはいられない気持ちになります。しかし、その背後には苦痛でおどろおどろしい自然淘汰の歴史があり、個々の生物はその苦痛に満ちた歴史をまたもう一度、反復強迫的に繰り返そうとしているのです[23]。
さて、これまで述べたことをもとに、ここで意識についての暫定的なモデルを提案してみたいと思います。
フロイトが考えたように、意識は知覚と結びついた現象であると仮定します。知覚というプロセスは、受動的なものではなく、外界に対する予想や期待を能動的に投げかけ、それが外からの刺激と出会ことであります。ここで投影されるものは個人的な過去の記憶ですが、その背後にある太古の遺産が、われわれ自身が思っている以上に大きな影響をおよぼしていると想定されます。さらにこのような外界に対する予想は、基本的に外傷的な性質の体験を反復しようとする営みです。それは個人においても進化過程においても、過去に経験された過酷な環境を投影することです。害をおよぼさない刺激を記憶する必要はありません。生命を乱すような刺激についてのみ記憶痕跡に残し、それをもとに現在の外界を予想して来るべき脅威に対して準備する必要があるのです[24]。
例として「人の顔を見る」ということを考えてみましょう。われわれは毎日いろいろな人の顔を見てそれが誰かを識別し、表情を読み取ります[25]。みなさんが知人の顔を識別できるのは、過去に見たその顔の特徴を覚えているからです。その表情から感情を感じ取れるのは、過去に多くの人と交わした表情についての膨大な経験の蓄積があるからです。これらの記憶は単なる個人的なものとはいえず、文化や言語を超えて普遍的な様相をもっています。感情が表情に表現される様式が異なる文化間でも概ね一致していることや、生まれたばかりの赤ちゃんがすでに顔を特別なものとして認知しはじめるといったことから明らかなように、顔についての基本的な知識は人類共通の太古の遺産といえましょう。ヒトにとって表情というコミュニケーション手段がこれほど重要な位置づけにあることは、かつてわれわれの祖先が、表情による意思伝達能力が生存を左右するような環境(そのような淘汰圧)におかれていたことを意味します。なかでも重要な要因は、人間がきわめて未熟な状態で生まれてくるということでしょう。自力ではなにもできない赤ん坊にとって、表情によるコミュニケーションは養育者の保護を引き出す手段として極めて重要なものだからです。
今この瞬間の知覚プロセスは、生命誕生からの35億年の歴史が現在と出会うことです。これは比喩でも誇張でもなく字義通りの真実です。人間の高度な認知能力を作り出すのには、最初の生命から現在に到る自然淘汰のすべてのステップ(それぞれの段階の生物が厳しい環境を生きぬいてきた体験)が不可欠でした。この太古の遺産に個人の体験が上乗せされた記憶から、現在の外界が予想され投影され、現実の外界と出会います。その際に、途中の細かな過程はさておいて、結果としてはおおまかに3つのことが起こると考えられます。第一になんらかの行動がとられること。第二に新たな記憶痕跡が残されること。そして第三に意識が生じることです。(ここで「第一」から「第三」に順序としての意味はありません。)
「客観的には記述不可能な意識」という最初の問題に戻ると、意識の生成ということを仮定せずに、行動と記憶ですべてを説明するという立場もありえるでしょう。しかし、ここでは行動や記憶と同じレベルで意識というものが存在すると仮定してみます。そして、それはフロイトの言うように記憶の代わりに生じるのだとします。記憶は後に残し伝えるものだとすると、意識はそれらを消し去って無にするものです。個人においても進化過程においても、記憶の蓄積はより複雑な葛藤と高度なレベルでの緊張をもたらします。そのようにして生じた興奮は、個人においては意識化という過程によって消失します。(進化過程においては個体の死によって消失するのかもしれません。)意識とは、太古の遺産を含む過去の記憶が、現在の現実と出会って生じる火花のようなものでしょう。意識は、その内に全生命の歴史を凝縮して表現します。それ自体一瞬にして消え去りますが、連続して生じる意識は記憶の助けによって見かけ上の連続性をもつのです。
最後は抽象的で雲をつかむような話しになってしまいました。次回のセミナーでは、このモデルを基礎に人間における特異性ということについて、もう少し具体的な方向に肉付けをしてみたいと思います。今回も少し触れましたが、ダーウィンの性淘汰理論の視点から、フロイトの欲動理論に新たな光を投げかけてみる予定です。