フロイト・セミナー応用篇
第4回 進化論から見たナルシシズム
重元寛人
このシリーズのセミナーではこれまでフロイトの欲動理論を進化論の観点から再検討してきました。今回はナルシシズム理論について、性淘汰との関連から考察をすすめたいと思います。
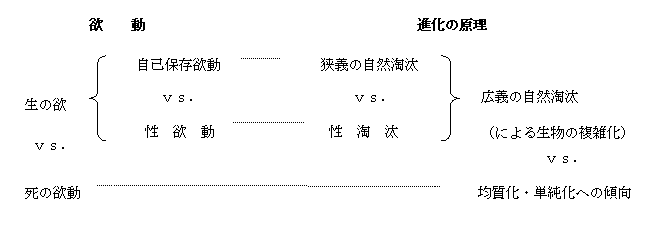
ここに示したのは、第2回のセミナーで示した欲動と進化様式の対応図式を若干改変したものです。フロイトは、精神のダイナミックな様相を自己保存欲動と性欲動の対立として、さらに生の欲動と死の欲動の対立としてとらえていました。これらを進化の原理と対応させたのは私自身のアイデアですが、フロイトの思考にそういった要素がなかったわけではありません。第一に、彼は欲動を生物学的な基盤をもつ概念として規定しています。第二に、『快感原則の彼岸(1920)』での議論では、欲動の対立という見方をもっとも単純なものも含む全生物に広げ、さらに生物の進化に対しても同様の視点を適用しています。
『欲動とその運命(1915)』では、欲動を、心理学の構築に必要不可欠でありながら、その時点では暫定的で不明確な基礎概念として規定しています。自己保存欲動と性欲動の対立という捉え方も、精神分析の経験をもとに神経症理論を構築する上で必要となった作業仮設にすぎません。一方で、フロイトはこの分類が生物学と矛盾するものではないことも指摘し、次のように述べています。
生物学は、自我と性の関係について二つの異なる見解があり、どちらも同等の正当性を備えていることを明らかにしている。一方の見解では、重要なのは個体であり、性は個体の営む活動の一つで、性の満足は個体の欲求の一つであると考える。もう一つの見解は、個体とは、ほぼ不滅な胚原形質の仮初の付属物にすぎず、生殖プロセスによって個体に胚原形質が委ねられているにすぎないと考える。
『欲動とその運命(1915)』ちくま学芸文庫フロイト自我論集p.23
生物学における二つの見解の併存と対立は、現代において一層鮮明になってきています。『利己的な遺伝子(1975)』で生物学に新たなパラダイムをもたらしたリチャード・ドーキンスは、ネッカー・キューブの例えを用いてこのことを述べました。
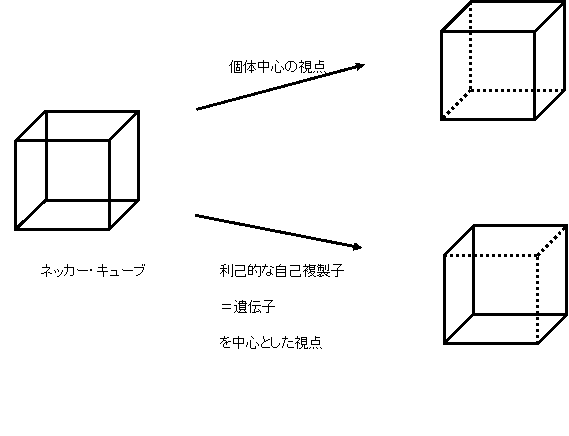
ネッカー・キューブとはここに示したような線画で、見方によって2種類の立方体の透視図に見えます。ドーキンスは、従来からの個体中心の視点に対して、利己的な自己複製子としての遺伝子を中心に据えた生命観を提示しました。新たな視点から見ると、生物の個体は遺伝子のコピーをより効率的に伝えるために利用されるヴィークル(乗り物)にすぎないということになります[1]。
個体を中心にした視点から見ると、自己保存への欲求と生殖に向かう欲求は時として相互にするどく対立するものです。しかし利己的な遺伝子の視点からは、双方ともに自らのコピーをより多く残すという単一の目的に奉仕するために個体に付与されたという点では変わりありません。ある条件においては個体の生存が優先され、別の条件では危険を冒しても生殖を行うことが優先され、最終的に遺伝子の増殖にとって最大の効果がえられる決定がなされる。そういう意味でこの葛藤は、調和を乱すものではなく、より適応的な行動を選択するためのしくみであるといえましょう。
欲動という暫定的な概念は、今なお充分実用的なものであると私は考えています。脳の基本単位たるニューロンの微細な構造と機能およびそれらの脳内での配置と働きが解明されつつありますが、それがどのような過程を経て最終的な行動につながっているかという中間項目については依然として大部分ブラックボックスのままなのです。また、遠い将来にそれらの長い鎖が完全に解明されたとしても、人間の頭脳でその意味を直感的に理解できるものでしょうか。
そこで、実際的で暫定的な心理学的概念が必要となるのですが、それが現代的なものであるためには脳についての生物学的な知見と矛盾しないという条件を満たさねばなりません。とりわけ重要な項目として、脳がニューロンという基本単位によって構成されていることと、それが進化過程によって作られたということの2点をあげておきましょう。そして、フロイトの欲動理論は実は最初からこれらのことを視野に入れているのです。
精神分析以前の『失語論』および『科学的心理学草稿』でなされたニューロン・ネットワークによる心理学の構想は、メタ・サイコロジーの背後にも脈々と流れており、いくつかの点で現代の脳科学をも先取りしています。例えば葛藤状況にある諸欲動がどのような運命をたどるかはリビドーの配分の量的なファクターによって決まるという経済的視点は、個々のニューロンにとって興奮を他のニューロンに伝えるかどうかが、興奮系と抑制系のシナプスによってもたらされる膜の脱分極の電気的な総和によって決定されるという事実にマッチしています。
欲動理論を進化論との整合性から吟味することが本シリーズのセミナーの主題ですが、とくに性淘汰との関連ということに注目しています。性淘汰とは、ダーウィンが『人間の進化と性淘汰(1871)』の中で提唱した進化の様式であり、生殖をめぐる雄どうしの闘争と雌の選り好みによって働く淘汰のことです。ダーウィンは、昆虫にはじまり魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類と広範囲にわたって性淘汰を研究し、分類学上大きく異なる動物間にもしばしば共通にみられる傾向を発見しました。それは、雌よりも雄の方が大きな体をもち闘争的であること、美しい色彩や装飾的な付属物をもつこと、求愛のために特徴的な鳴きかたをしたり、ダンスをしたり、あるいは緻密な巣を作ったりすることです。これらの形質が性淘汰によって、すなわち雄が闘争し雌が選り好みをするという基本的なパターンによって獲得されたというダーウィンの仮説は、さまざまな実証的研究や数理学的モデルによって検証されてきました。
性淘汰は、根本的には生殖にまつわる雌と雄の投資の違いによって生じます。雄の作る精子は小さくて多いが、雌の作る卵子は大きく少ない。雄は不確実だが多くの子孫を残す機会を与えられるのに対して、雌は比較的少数の子孫を確実に残すことができる。これらの事実によって雄と雌とで配偶に関する基本戦略に違いが生じるのです。雄にとって重要なことは、より正確に言えば雄の体内にある遺伝子たちにとって重要なことは、なるべく多くの雌と配偶し他の雄に奪われないよう独占するための戦略です。一方、雌にとっては、限られた数の子の質を高めるために、なるべく適応的な配偶相手を選ぶことがより死活的な問題になってきます。動物界に広くみられる、雄より雌が強く選り好みをする傾向はこのように説明できるわけです。
人間が他の類人猿との共通の祖先からいかにして進化したかという大問題について、ダーウィンは性淘汰との関連から論じようとしました。ただ、この時代には前提となる考古学的な証拠や地質学的知識が乏しかったこともあり、また彼自身の慎重な性格もあり、最も本質的なところについてはあいまいな記述となっています。近年、ダーウィンの思考をヒントに、「ヒトにおける巨大な脳と高度な知性は性淘汰によって進化した」という仮説がさまざまな形で提出されるようになりました。前回のセミナーでは、これらの説を紹介した上で、人間の行動を規定する要因として性欲動の重要性とその流動性を強調したフロイトの欲動理論と比較し、その類似性について言及しました。
今回は、ナルシシズム(自己愛)という概念について検討してみます。『ナルシシズム入門(1914)』において、ナルシシズムは「自己保存欲動のエゴイズムをリビドー的に補強するもの」と規定されています。つまり、ナルシシズムは単に個人の利益の追求をめざすものではなく、そこに性愛的な要素が加味されているというところにこそその本質があるのです。彼の提示したナルシシズムの発達モデルをしめします。
一次ナルシシズム
↓
対象備給の段階
↓
対象喪失
↓
対象との同一視
↓
二次ナルシシズム
一次ナルシシズムはリビドーが原初的に自我に備給された状態です。対象愛の段階ではリビドーは対象に備給され、そのことで欲動は特定の対象の知覚イメージと結びつきます。対象喪失の場面において、自我は対象に備給されたリビドーを撤退させて再び自らにふりむけるのですが、その際に失われた対象を自己の中に再生する試みとして同一視という過程がおこるのです。同一視によって、二次ナルシシズムは生き生きとした具体的なイメージをともなうものとなるのです。もちろんこれは単純化したモデルであって、実際には対象愛と二次ナルシシズムは相互に行き来しながら複雑な発達をとげます。愛する対象をとりこむことでナルシシズムは豊かになり、ナルシシズムを投影することで対象愛は共感に満ちた豊かなものになっていくのです。
以上のモデルを進化論の見地から検討してみましょう。ダーウィンの時代には、人間を含むすべての動物が、神によって創造されたのではなくて自然淘汰によって進化したということが大きな議論になりました。現在では、個人的信念は別として、この点が学問的な議論になることはあまりありません。しかし、私たちは非常に巧妙にできた生物のしくみを見ると、誰かがそれを計画したとか、そこにはある種の目的があるとか、それがある方向に向かって進んでいるといった風に、つい考えたくなってしまいます。「進化」という言葉自体がそのような誤解のもとをはらんでいるとも言えます。自然淘汰による進化ということがどういうことかを直感的に理解するのは以外にむずかしいのです。例えば、時計でも自動車でもコンピューターでも、人間によって作られたものは製作途中の段階ではほとんど機能しません。これに対して、すべての生物は、地球上に最初の生命が誕生してから現在まで常に完全に機能する状態を保ちつつ、少しずつ改造することで現在の形質を獲得してきました。その過程にはどこが途中でどこが完成ということはありません[2]。例えば、魚が陸に上がるにあたって、「今鰭を脚に進化させている途中です、まだ役には立ちませんがいずれ完成したら陸上を歩行するのに便利でしょう」とか、鳥に進化しようとしている恐竜が「今は邪魔なだけですが前脚がずいぶん羽らしくなってきたのでいずれ飛べるようになるでしょう」などということは決してなかったということです。後から見ると「途中」にみえるあらゆる時点において、それぞれの器官は完成し役に立っていたといえましょう[3]。
役に立たない「製作途中の状態」をもたないということは、進化過程における大きな制約となりますが、そのかわりに「前適応」ということがしばしばおこります。これは、すでにある器官がもともととは別の機能に利用されるようになり、その第二の機能が向上するように進化が進んだ結果、以前とは別の機能を担う器官になっていくという過程です。具体例としては、魚が陸でくらす動物に進化する際に、浮き袋が肺になり、胸鰭と腹鰭が四肢に変化したということがあげられます。
つまり進化というものは古い形態と機能の上に新しいものを加えながら変化していくことであり、例えて言えば小さい家に住みながら少しずつ増築を重ねて大きな家にしていくとか、ほんの一行のコンピューター・プログラムからはじめて機能する状態を保ちつつ一行ずつ追加して大きなプログラムにする[4]というようなものでしょう。大きくなった状態だけを見ると、ずいぶん無駄も多く、「もっとここはこうした方がすっきりするのに」と思えるところもあるでしょうが、それはそんなやり方でしかできないから仕方ないわけです。最後にコンピューターの例をあげたのは、もちろん動物の脳ということを考えるためです。脳というような非常に汎用性の高い器官においては、先ほどから述べてきたような古い機能に新しい機能を追加したり、古いやり方を新しい機能のために利用したりといったことが広範に行われていることが推測されます。人間における脳の形態を見ても、古い起源をもつ皮質を新しい皮質がとりかこむような構造をしているわけで、その機能たる精神活動も古い原理と新しい原理が入り混じりつつ働いているものと想定されます。
欲動ということを進化的視点から検討してみると、自己保存欲動は生物に普遍的な、もっとも原始的な欲動といってよいでしょう。性欲動は性の区別が生じた時点にまでさかのぼることができるから、やはりかなり古い起源をもつ欲動でありましょう。実際、これら2つに相当する本能は、動物界の広範囲の種に観察されています。では、ナルシシズムについてはどうかというと、これに相当するものを他の動物がもっているのかどうか観察によって判断するのはむずかしいことです。ただ、対象愛がナルシシズムにとりこまれ、ナルシシズムが対象に投影されるといった、自己認識および対人関係の複雑な発展は、人間に顕著な特長であるといってもいいでしょう。そういう意味で、ナルシシズムは人類の歴史上比較的最近になってから発達をとげた新しい心的状態であり、これこそが高度な文明の基盤をもたらしたのではあるまいかと仮定してみたくなります。さらに、ナルシシズムは新たに一からつくりだされたものではなく、古くからある自己についての利己的な態度と、他者、特に性的対象に向けられた態度とを利用して発展させたものであり、精神機能における前適応の一例とも言えるのではないでしょうか。このように、ナルシシズムは、原始的な欲動のエネルギーを利用して新しいことを実現しようとするために、全体としてはいびつで不安定なものになりがちです。ナルシシズムの発達によって、対象と自己は同等のものと認識されます。すなわち、古くから対象にとってきた態度が自己に適用され、古くから自己にとってきた態度が対象に適用されます。このことを、ナルシシズムの男女差という問題の中にみてみましょう。
フロイトは心的特性の男女差という問題にたびたびとりくんでおり、『ナルシシズム入門』においても男性に多い依託型対象選択と女性に多いナルシシズム型対象選択といったモデルを提示して論じています。今回はその議論も参考にしつつ、ナルシシズムそのものの男女差ということについて考察してみましょう。ただし、これから述べるのはあくまで単純化したモデルであり、現実の人間がさまざまな比率で両性の特徴をもつことはいうまでもありません。
原則として、ナルシシズムにおいては対象への態度が自己への態度に反映します。男性は、対象を充分な吟味のないままに容易に理想化してしまい、その獲得にむけて邁進する傾向があります。対象をどれにするかについての迷いは少ないが、対象を獲得できるかどうかは不確実で自信がない。これは、性を持つ動物の雄にみられるかなり普遍的な特徴であって、これまで説明したように性淘汰によって進化してきた性質といえます。このような男の対象への態度を自己に適用すると、男性のナルシシズムは自己を十分吟味しないままに理想化してしまいその実現をめざすが、実現できるかどうかについては自信がない、ということになるでしょう。
一方、女性は対象を比較してすぐれたものを選び取るということに重きをおきます。これは、性を持つ動物において雌の方が選り好みをよくするということと対応しています。この態度が自己に向けられると、ありえる自己像の選択肢を比べてより優れたものを選び出そうとする、「自己についての選り好み」をまねきます。自分以外の女性は自己像の選択肢のひとつとみなされるので、これは結果的に自他を比較する態度となります。自分が選ばれることには自信があるが、いかなる自己像を採択するかについて迷うのが女性のナルシシズムの典型といえるでしょう。
女性が自己像についての選り好みをしていることを、現在の一般的風俗の中に反映している例をひとつあげましょう。ほとんど一方の性の読者を想定して作られる雑誌の比較です。いわゆる「男性誌」というものを開くと、そこにはたくさんの素敵な女性の写真が載っています。男性は女性に関心があることがわかります。ところで、「女性誌」の方を開くと、ここもまた素敵な女性を紹介した写真や文章であふれているのです。女性は、女性自身に関心があることがわかります。