フロイト・セミナー応用篇
第5回 進化論からみた集団心理
重元寛人
われわれがよってたつ心理学の多くは、個人というものを、固有の感情、欲求、思考を有し、それらに基づいて行動する基本的な単位とみなしています。これらの前提について充分に吟味されることが少ないのは、われわれ自身、自分の心がこの体につつまれて存在していると感じており、また目前に現れる身近な人々も同様の存在であると自然に思われるからでしょう。しかし、実感と合うからそれが正しいとはかぎりません。物理学においては、われわれの日常的感覚に合致する古典力学が最初に生まれましたが、それは人間の知覚をはるかに超えるほど巨大な、あるいは微細な事象を説明するには不正確であることが後に判明し、相対性理論や量子力学の発見の契機となりました。心理学において個人というものが最初から基本的なまとまりをなしている、という前提に、一度は疑いの目を向けてみてもよいのではないでしょうか。
集団の中の個人が、分離された状態とは違った、退行的な行動をとることは、「群集心理」としてよく知られています。この現象を、個人心理学の見地から説明することももちろんできます。一方、集団全体をひとつのまとまりとしてとらえ、その動きを観察し、記述し、そこに法則性を見出すという、集団心理学あるいは社会学という学問体系もあります。集団心理学的な視点から、もう一度個人の心理というものを眺めてみる。さらに時間という要因を加えて、進化論的視点から検討してみる。すると、現在および過去の膨大な個人とつながる諸要素によって構成される個人という、新たな像が浮かび上がってきます。以上のような試みは、ジクムント・フロイトが1921年の著作『集団心理学と自我の分析』においてなしているところであり、今回はその論旨を追いつつ、現代的な視点も加味して検討してみましょう。
フランスの社会心理学者ギュスターヴ・ル・ボンは、1895年の著書『群集心理』において、従来から観察され指摘されていた、集団内におかれた個人の特異な振る舞いを鮮やかに描き出しました。彼によれば、群衆中の個人の主要な特徴とは、意識的個性の消滅、無意識的個性の優勢、暗示と感染とによる感情や観念の同一方向への転換、そして暗示された観念をただちに行為に移そうとする傾向であるといいます。
ル・ボンが「群衆」と呼んだものを、フロイトは心理学的集団と定義しました。それは単なる人の集まりではなく、互いに心理学的に結びついてひとつのまとまりをなします。心理学的集団は、ひとりの指導者をもちます。その指導者は現実の人物でもいいし、宗教における神のように非現実的な存在であってもよいのです。
このように規定した上で、フロイトは集団内の個人同士を結びつける接着剤の役割をしているものはなにか、という問いかけをします。その答えは当然、リビドー、よりおだやかな言い方をすればエロスということになります。
リビドーによって結びつくといっても、2種類の結びつき方があります。個人は、指導者にほれこみ(Verliebtheit)によって結びつきます。彼はおのれの自己愛を放棄して指導者に投げかけ、これを理想化します。さらに、彼は指導者を自我理想のかわりにしてしまい、その命ずるところ何事にも服従するようになります。指導者に愛情をむける個人には無数のライバルが存在するというこの状況は、通常であれば強烈な嫉妬をひきおこすはずですが、心理学的集団においては個人相互が同一視(Identifizierung)によって結びつくことによってそれが回避されます。すなわち、集団内の個人は同一であり、指導者によって平等に愛されると感じるのです。
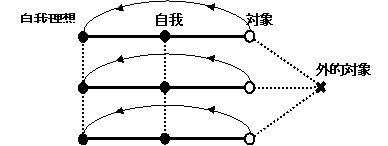 |
フロイトが作った図式を示します。彼は「一次的な集団とは、同一の対象を自我理想とし、その結果おたがいの自我で同一視し合う個人の集りである。」と述べています。
以上は、リビドー理論によって集団心理を見事に分析したものですが、彼の論文はこう単純には終わりません。続く歴史的考察では集団心理の方から逆に個人心理をみていくことになります。
しかしそこに入る前に、自我理想という概念の変遷についてみておきましょう。
1914年 『ナルシシズム入門』
1917年 『悲哀とメランコリー』
1921年 『集団心理学と自我の分析』
1923年 『自我とエス』
自我理想について言及した主な論文を示しました。『ナルシシズム入門』で、それは「理想的な自我」として登場します。幼児期の誇大妄想の段階で自我に向けられていたナルシシズムは、現実認識の高まりとともに自我理想にひきつがれることになります。『悲哀とメランコリー』では、メランコリー患者において自我理想が自我を責めさいなむ様相が描写されました。こうして自我理想においてはその輝かしさよりも、暗黒面に注目が向けられるようになりました。『自我とエス』では、「超自我」と名前を変えることで、より無意識的な方向に概念を拡張され、さらにそこを支配するのは「純粋培養された死の欲動である」とまで言われることになります。
進化論的視点に移りましょう。フロイトは『トーテムとタブー』において、人類の祖先は一人の強大な男性が支配する群れの中で生活していたという、ダーウィンの仮説をもとに、エディプス・コンプレクスの歴史的再解釈を行いました。
『集団心理学と自我の分析』では、このような歴史的背景をふまえた上で次のように述べています。
集団とは、原始群族の再生のようなものである。あらゆる個人の中に原始人が潜在していて、任意に群れをなして集まると、原始団体がそこに再現されるのである。
引用を続けましょう。
われわれは、集団の心理とは最古の人間の心理である、と言わねばならない。われわれが、集団の名残を一切無視して個人心理として孤立させていたものは、のちになってはじめて、徐々に、いつもただ部分的に、古い集団心理から取り出されたものである。
ここでは、古い集団心理というものを、個人の心より根本的なものととらえるという、驚くべき視点の転換がおこっています。さらに、この少し先で彼は別のことを述べています。
そもそも個人心理は、集団心理とおなじくらい古いにちがいない。なぜならば、最初から二種の心理、すなわち、集団中の個人の心理と、父、首領、指導者の心理があったからである。
ここに述べられた意味を理解するために、2年後に書かれた『自我とエス』から引用しましょう。
昔、父コンプレクスによって宗教と道徳を獲ちえたのは原始人の自我なのか、それとも原始人のエスなのか?(中略)自我の体験は一見すると、継承されないで失われていくようにみえる。しかし、もしその体験が、しばしば、充分な強度をもって、世代を追ってつづく多くの個人に繰りかえされるならば、それはいわばエスの体験にかわり、その印象は遺伝によって保存される。したがって遺伝性のエスは、その中に数えきれないほど多くの自我存在の残余をかくしており、自我がその超自我をエスから作るとき、おそらく、ただ古くなった自我の像を出現させ、復活させるのであろう。
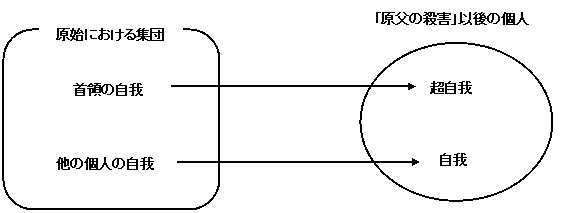
これらの引用をまとめてシェーマにしてみました。原始群族には首領の心理と他の個人の心理が存在しました。これは、「首領の自我」と「他の個人の自我」と言い換えてもよいでしょう。首領も他の個人も祖先から受け継いだほぼ共通のエスを持っているはずであり、この同じようなエスからあるものにおいては首領の自我が、大多数においては他の個人の自我が出現します。どちらが出現するかは集団内の競争関係によって決まるのであって、それぞれの個人は両方の可能性を潜在していたでしょう。
現在の人類においては、首領と他の個人の明確な分化はなくなりました。それは、フロイトの言うところの「原父の殺害」という歴史過程によって、首領の機能の一部がトーテムや宗教などの抽象物に移され、首領の自我をそのままに体現する者がいなくなったかわりに、個人がそれぞれに首領の自我の名残すなわち超自我を抱くようになったからでしょう。
以上のような流れを踏まえて、フロイトが最終的に達した心的装置の有名なモデルを眺めてみましょう。
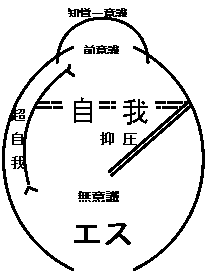 |
個人の心理は、エス、自我、超自我の3つの審級により成り立ちます。論文『自我とエス』で強調されていることは、われわれにとってもっとも身近に感じられる自我が、見かけ上の主体性とは逆に、一番依存的であり、外界、エス、超自我と3方向からの要請によって従属的にその振る舞いを決められているということです。エスと超自我が、遺伝的背景を持った確固たる存在であるのに対して、自我は外界における他の自我と同一視しつつ、ということは風見鶏のように流行に身をまかせて、多彩な表現型をもちます。精神疾患の時代による変遷といったことも、このような自我の流動性によってもたらされる現象でありましょう。