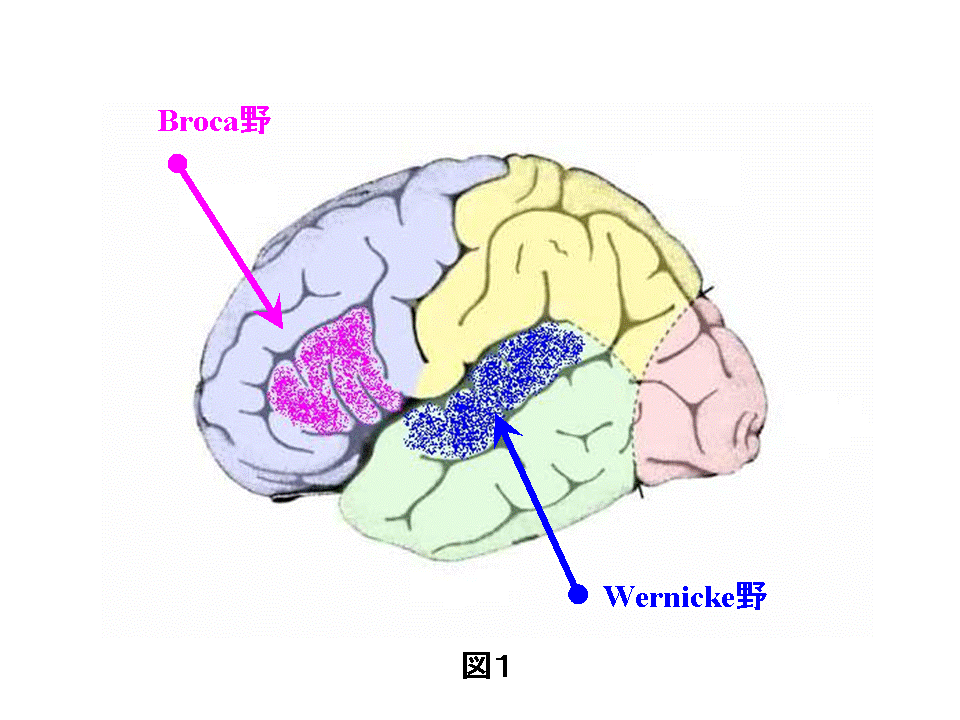
フロイト全集 第1巻 1886-94年
フロイト全集の第1巻は、脳科学者フロイトが精神分析を生み出していく大変興味深い過程を示した諸論文を含んでいる。なかでも、失語症の論文を含めたことは今回の邦訳全集の大きな特徴となるだろう。この著作は、フロイト存命中に出版が始まったドイツ語版全集にも英訳標準版全集にも含まれていない。心理学的な著作ではないというフロイト自身の意向を反映してのことであった。しかし、失語症論文は後に展開されるメタ・サイコロジーにおける言語論などともつながりを持っており、とても重要なものなのだ。
他の論文や文章を読んでも、フロイトの脳科学者としてのすごさ、そしてその彼がなぜ心理学へと歩をすすめていったのか、といったことをいろいろ考えさせられる。
失語症の理解にむけて――批判的研究
Zur Auffassung der Aphasien (1891)
中村靖子 訳
この著作は、フロイトが単独で出版した書籍としては最初のものであり、執筆当時はかなりお気に入りの作品であったようだ。
当時は、脳についての研究や議論がものすごく盛んで、そういった意味では現代の状況とちょっと似ている。そして、注目されていた主要な題材のひとつが、失語症であった。フロイトの叙述に従って、年代順に簡単にまとめると以下のようになる。
1861年 ポール・ブローカの発見。大脳の左下前頭回の損傷によって、音声による言語の表出が失われる。(正しくは左側ではなく優位半球側だが、優位半球は左であることが多いので、以下でも「左」と記すことにする。)
1874年 カール・ヴェルニケ、『失語症複合』を発表。左上側頭回の損傷によって、音声言語の理解が失われる。大脳における言語装置は、言語の感覚中枢(左上側頭回:ヴェルニケ野)と運動中枢(左下前頭回:ブローカ野)と、それらを結ぶ伝道路によって成り立つという仮説を提示した。(図1参照)
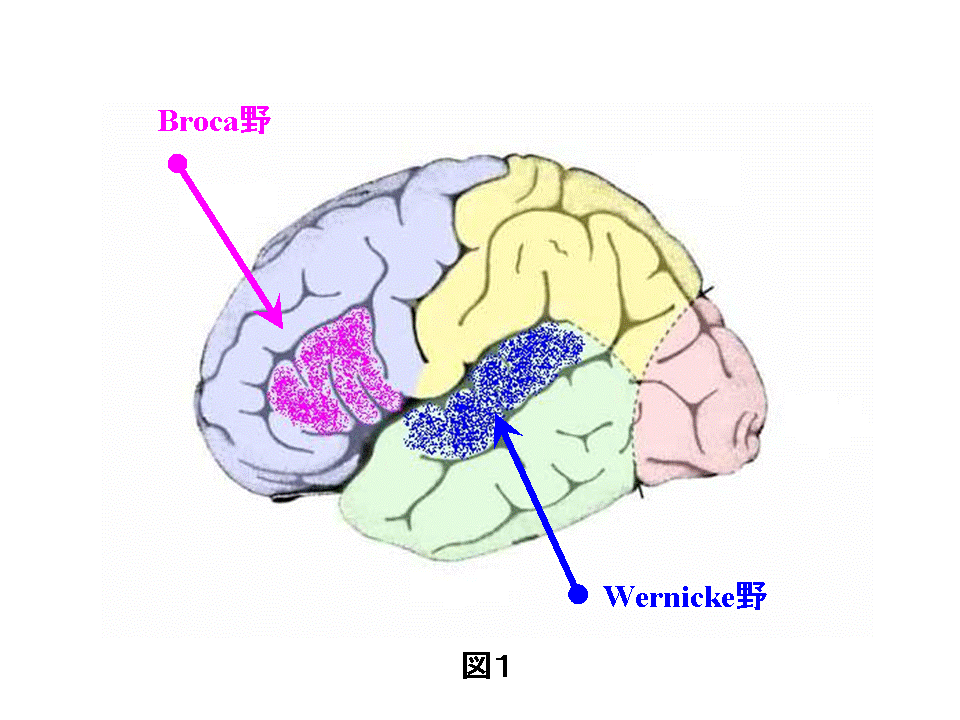
1885年 ルードヴィヒ・リヒトハイム、『失語について』を発表。その中で、失語についての有名な図式と、それに基づいた失語分類を提示した。(ヴェルニケ−リヒトハイムの図式およびヴェルニケ−リヒトハイムの失語分類:図2)
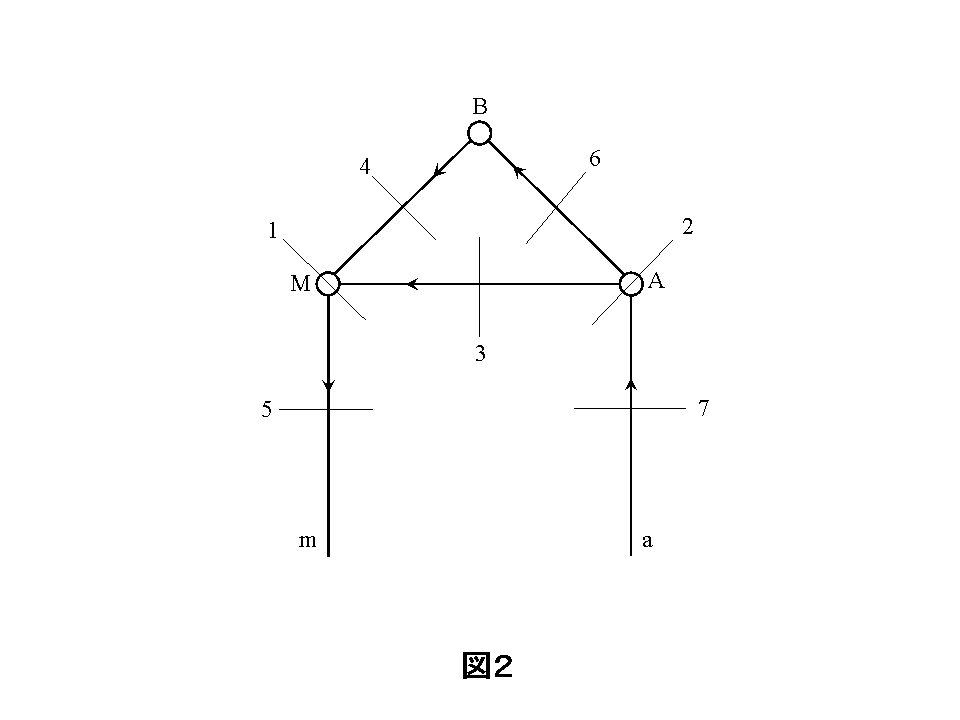
A:聴覚性言語中枢(ヴェルニケ野)
M:運動性言語中枢(ブローカ野)
B:脳の特定部位を示すのではなく、言語装置を起動するような大脳皮質の無数の部位を代表する。
図中の1〜7の損傷によって、以下のようなタイプの失語が生じる。
1.皮質性運動失語(ブローカ失語):言語理解は保持されるが、自発的に話すことも復唱することもできない。
2.皮質性感覚失語(ヴェルニケ失語):話しかけられたことを理解できず、復唱もできない。自発的に話すことはできるが、意図する語と違う語を発してしまうという錯語を生じる。
3.ヴェルニケ伝導失語:理解も発語もできるが、錯語がみられる。
4.超皮質性運動失語:自発的に話すことはできないが、復唱はできる。
5.皮質下性運動失語:自発語が失われる点で皮質性運動失語に似るが、書字能力は保持される。
6.超皮質性感覚失語:話しかけられたことは理解できない。復唱はできるが、復唱した内容を理解しない。自発的に話すことはできるが錯誤が混じる。
7.皮質下性感覚失語:皮質性感覚失語に似るが、話す際に錯語がみられない。
以上は、フロイトのサマリーをさらに要約したものである。実は、このような説明は、失語症についての古典的分類として今なお立派に通用しているのだ。そういう意味では、ヴェルニケとリヒトハイムの業績は実に立派なものであったといえる。
フロイトによる批判
フロイトが本論文で試みているのは、ヴェルニケとリヒトハイムの大理論に対する批判なのであった。当時から見ると、失語症の大御所に若造が楯突いているようなものであったろうが、それは堂々たる論陣の張りようだった。
問題は、脳の働き方についての局所論か全体論かという、当時からあり現在も続いている論争に通じるものである。局所論とは、脳の働きを局所における個々の機能に分解して説明しようとする立場であり、全体論とは、脳における重要な働きは局所の働きには分解できない全体的なものであるとする立場である。
フロイトは、どちらかというと全体論の立場から、ヴェルニケやリヒトハイムの局所論的な捉え方を批判した。当時全体論的、機能的に失語現象を捉えようとして学者としては、フバート・G・グラースハイ、チャールトン・バスティアン、ジェームズ・バスティアンがおり、本論文でもそれらの著作から多くの引用がなされている。また、フロイトの論を支えた根本的な考え方としては、ヒューリングス・ジャクソンからの影響が大きい。
ヴェルニケは、言語機能を、「聴覚性言語中枢」や「運動性言語中枢」といった、複数の「中枢」と、それらを結ぶ伝導路という具合に分解して考えた。そして、聴覚性言語中枢には、音声言語の記憶である「語音心像」が、運動性言語中枢には発語に関わる記憶像である「語運動心像」が、それぞれ蓄えられているという。それぞれの記憶心像は、個々の神経細胞内に蓄えられていると、ヴェルニケは考えた。この考え方は、神経解剖学の権威であったテオドール・マイネルトの論にもとづくものである。ちなみに、マイネルトはフロイトのかつての師にあたる。
以上のような仮説はとても明快であるが、実際の失語症の臨床とは合致しないところが大きい。フロイトの詳細にわたる批判をごく大まかに要約すると、次のようになるだろう。
理論と現実が特に大きく異なるのは、聴覚性言語中枢が損傷されるという、ヴェルニケ失語である。このタイプの失語では、聴覚理解は失われるが発語は保たれるということになっている。ところが、実際にはその発語は、とても「無傷」と言えるような代物ではないのである。
まず、意図する語が別の語に置き換わる錯語が頻繁にみられ、時にはほとんど意味不明な「ジャルゴン失語」を呈することもある。「あれ」や「それ」などの不特定の名詞が多く、付属的な言葉が過剰で、同じ語の繰り返しが多い。ヴェルニケ自身が提示した、すでに相当の回復をみせた症例の言葉は次のようなものであったという。
「とてもとても、あなたがとにかくご覧になったすべてにお礼を‥‥。本当にとてもありがとうございます、あなたが私におっしゃってくださったことすべてに。ねえ、あたなたがこんなによい方でいらっしゃって、あなたがこんなに親切でいらっしゃって、本当に何回もお礼を申し上げます。」(1-30)
要するに、「聴覚性言語中枢」なる独立した中枢が存在するという仮定そのものに無理があるのであって、言語の理解と発語といったことは一連の密接に絡み合った機能と捉えた方が自然なのである。
フロイトは、単に批判するだけでなく、代案も提示している。
言語機能は、左半球の、ヴェルニケ野やブローカ野を含むより広範な領域全体において、連合的になされている。ヴェルニケ野が、見かけ上「聴覚性言語中枢」のように見えるのは、この部位が大脳の両側半球によって捉えられた聴覚刺激を束ねて受け取る場所であるからである。同様に、ブローカ野は、発語に際して、両側半球の発語に関連した運動野に向けて刺激を送り出す部位であるがゆえに、そこが損傷すると発語の障害がもたらされる。ヴェルニケ野とブローカ野以外の言語領域が部分的に損傷された場合には、残された領域が迂回路によって連合して機能しようとするため、換語困難(言葉が思いつかない)など、言語機能の全体的な低下をもたらすが決定的な障害には至らない。
すべては連合である
フロイトが最も痛烈に批判したのは、「神経細胞に表象が局在している」というヴェルニケの考え方であり、さかのぼればマイネルトの前提である。
記憶が、個々の神経細胞に蓄えられるなどということはあり得ない。ではどのように蓄えられるのかといえば、それは神経細胞同士の連合Assoziationによるのである。
これは、実に重要な、後の精神分析理論にも引き継がれる考え方である。"Assoziation"は、精神分析用語としては、「連想」と訳される。連想と連合は、同じものだったのだ!
概念と概念が連想(連合)によって結ばれているだけでなく、そもそもあらゆる概念、表象、感覚は、連合によってのみ成立するのである。
このことはなかなかピンときにくいが、心の働きを、脳の働き、それも神経細胞のレベルにまでさかのぼって考えていくと、それしかあり得ないということがわかる。
我々には、感覚を直ちに連合させることなしに感覚を持つことができない。どんなに我々が両者を概念的には明快に分けたところで、実際のところ両者は単一の出来事に付随したものであり、その出来事は、皮質にある一個所から始まり皮質全体に拡散するものなのである。したがって、表象にとっても連合にとってもその生理学的な相関項を局在するならば、同じ個所にあることになる。そして特定の表象を局在するということは、その表象の相関項を局在することに他ならないが故に、我々は、表象を大脳皮質のあるどこか一点におき、連合をそれとは別のある個所におくということを拒否せざるをえない。両者はむしろ、一点を出発点とするが、どの点にも終息せずに移動し続けるのである。(1-71)
つまり、視覚刺激であれ聴覚刺激であれ、それが感覚器官から大脳の神経細胞をある興奮させても、それだけでは「感覚」は生じないのであって、その刺激が神経細胞の連合によって他のさまざまな刺激と出会うところに、「感覚」という心的事象が生じるのである。
このような考えをたどっていくと、脳(身体)と心の関係という、根本的な問題にいきつく。
脳と心の関係
脳と心の関係がどうなっているか、ということは、不思議で、難解で、興味深い問題である。
昔から長い論争があるが、大きくは心身一元論と心身二元論がある。一元論の方は、主に唯物論であり、心というものも脳の物質的な働きとして一元的に説明できるというものである。二元論は、脳(身体)と心は次元の異なるものであるという考えで、古くからの、身体に心(霊)が宿るという捉え方と類似性がある。
フロイトはというと、二元論である。しかし、脳に無関係に独立した心があるという二元論ではない。むしろ、脳の物質的な働きに付随して、ある種の出来事として、心的な事象が生じるということらしい。
神経系における生理学的な事象の連鎖は、おそらくは心的な事象に対して原因と結果の関係にあるわけではないだろう。心的な事象が始まったからといって、生理学的な事象がそこで直ちに止んでしまうことはなく、むしろ生理学的な連鎖はそのままさらに続いていく。この連鎖の一つ一つの構成部分に(或いは複数の構成部分に)いずれかの瞬間からそれぞれ一つの心的現象が呼応するようになるというだけのことである。心的なものはしたがって、生理学的なものの平行現象なのである(「従属的共存付随現象」)。(1-68)
このような立場から見ると、「神経細胞内に記憶心像が貯蔵される」というマイネルトの考えは、脳における生理学的事象と心的事象とを混同した結果生み出されたものとなる。「表象」とか「記憶心像」といったものは、脳内の生理学的事象に付随して生じる心的事象であって、個々の細胞にとってはなんの意味もなさないのである。
語表象の心理学的図
すべての表象は連合として成立するわけだが、表象は大きく対象表象と語表象に区別され、その有り様が異なっている。その関連を示した図式を以下に引用する。
これが「心理学的図」であるというのは、例えば図における一つの丸が、脳のニューロンやニューロン群に対応するわけではないということだろう。丸自体も連合として成立しているから、脳の部分としては局在できないのである。
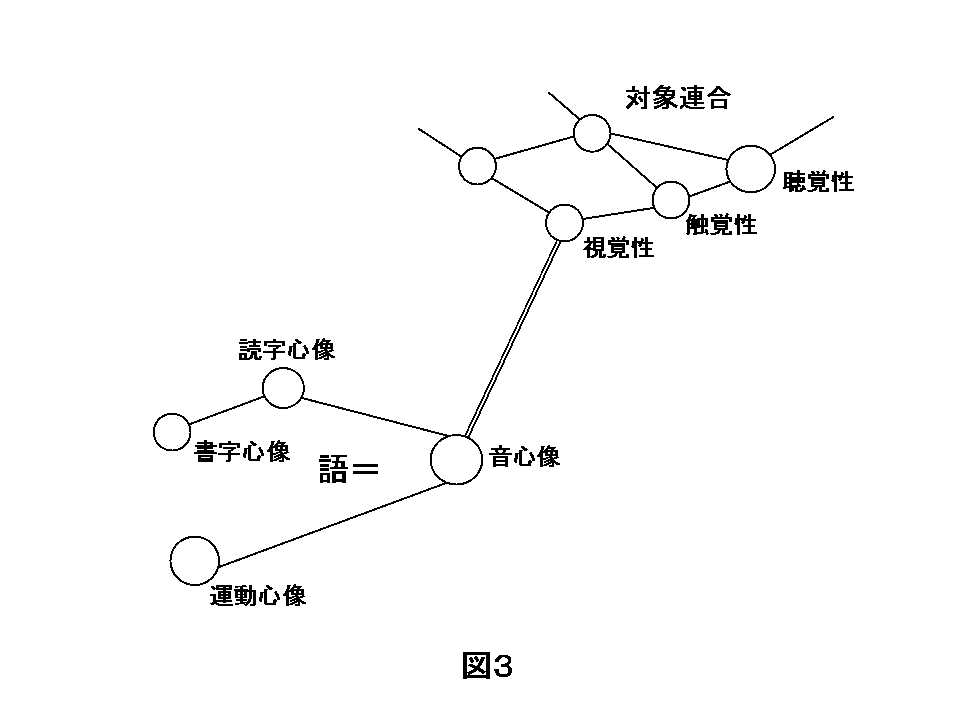
語表象は、それ自体で完結した表象連合である。それに対して対象表象は開かれた表象連合である。語表象は、その全ての構成要素からではなく、ただ音心像を経由してのみ対象表象と結びつく。音心像が語を代理すると同じような仕方で対象を代理するのは、対象連合のうちでは視覚的連合である。語音心像と、視覚的連合以外の対象連合との連絡は図に書き入れていない。(1-95)
「語表象は、それ自体で完結した表象連合である」とは、一つの語が比較的独立した連合として成り立っているということだろう。それに対して、対象表象は他の対象表象と密に連合して、全体で巨大な対象連合を作っている。この図の上の方は、そのような対象連合全体につながっていて、そこにたくさんの独立した語表象が結びついていることになる。対象表象から見れば、語表象との連合は、概念を区別してその論理的操作を可能とするのに役立つことになるだろう。
ここであげられた図式は、後のメタサイコロジー、例えば『無意識』(1915)における、語表象と対照表象についての議論にもつながってくるところである。
フロイトによる批判の妥当性
本書で展開されたフロイトの失語論批判が、脳科学の発達した現代的視点から、どれほどの妥当性をもったものであるかというのは興味深いことだ。私には、そのことを判断するに充分な知識もないが、それでもかなりいい線いってるのではないかと思う。
ヴェルニケ−リヒトハイムの図式や分類は、現代の失語の教科書にも載っているが、それにはあくまでも簡便な理解のためのモデルであるという但し書きもついている。実際の症例では、理論に当てはまらないことが多いのである。
言語中枢といったものがあるとしても、それはブローカ野やヴェルニケ野を含む、より広範な領域であるという点や、個々の神経細胞に言語表象が貯蔵されることはないという点では、フロイトは正しかったようだ。
しかし、フロイトが論じた、より根本的な言語の問題や、脳と心の関係については、今なお決着がついていないことが多いようだ。脳科学の大幅な進歩にもかかわらず、未だフロイトの思考に追いついていないというところか。
本書を読んでいると、フロイトはそのまま失語症の研究者としても充分にやっていけたのではないかとも思える。しかし、そうならなかった理由のひとつは、彼の思考があまりに先を行き過ぎていたということがあるのではなかろうか。科学の進歩には、根気強い検証を積み重ねていくことが不可欠である。天才は、その歩の遅さにつきあっていられなかったということではと。
H21.8.22 記
フロイトが奨学金で行った半年間の留学の報告書である。留学の主な行き先はパリのサルペトリエール病院であり、そこでジャン・マルタン・シャルコー教授に学ぶことが、当初から最大の目的であった。シャルコーは神経疾患の診療に熱心に取り組みつつ、若い医師や留学生を平等に受け入れて教育にも力を入れていた。その粘り強い診療と若い医師への分け隔てをしない人柄に、フロイトも「同じ立場にあった他の全ての外国人と同様に、シャルコーの無条件の信奉者となったサルペトリエールを後にした(1-136)」と述べている。
このシャルコーとの出会いが、若きフロイトの将来を決定づけた。
シャルコーの口ぐせは、「解剖学は大筋では完成し、神経家の器質性疾患に関する学説はおおよそは出来上がった。だから今度は神経症に取り組む番だ」であった。(1-137)
当時ヒステリーについては、詐病のような扱いをうけて真剣な医療の対象になっていなかったところもあるが、シャルコーは患者に真剣に向き合い、催眠を使っての治療を試みていた。フロイトもその診療に魅了され、帰国後にはしだいに熱意をもってヒステリーや他の神経症の治療に向かうようになったことは周知のとおりである。
H21.9.12
サルペトリエールへの留学でシャルコーに心酔したフロイトは、その講義録のドイツ語への翻訳と出版を師にもちかけた。訳者フロイトの熱意によってドイツ語版はフランスで原書が出版されるより前に出されたこと、そして構成も若干変更されてヒステリーについての講義が特に強調されていることが述べられている。
H21.10.22
パリからの帰国後、フロイトはウィーン医師協会で「男性ヒステリーについて」という講演を行い、それに続いてなされたのが本症例報告であった。アウグスト・Pと呼ばれる29歳男性の症例で、実際に本人を招いてのプレゼンテーションであったという。病気の経過について心理的な側面についても触れられるものの、後のヒステリー論文におけるような解釈はなく、現症についての詳細な描写が中心である。
H21.11.1
アーヴァーベック著『急性神経衰弱』書評
Referat über Averbeck, Die akute Neurasthenie, Berlin 1886 (1887)
渡邉俊之 訳
この時期のフロイトは、医学雑誌などに多くの書評を書いていたようだ。この書評でもそうだが、おおむね好意的な評価によって推奨している。
H21.11.1
ウィアー・ミッチェル(1829-1914)は、神経症性疾患に対する安静療法で有名な神経科医である。フロイトは安静療法について好意的に評価していた。
H21.11.1
先天性の聾唖者に対して、催眠術による治療を行い、聴力の持続的な改善がみられたという実践についての書である。もちろん、全ての対象に効果的であったわけではない。現代的な視点から見るとどうなのだろうか。自閉症のように聴覚への無関心な状態なども対象に含まれていたのではという気がするが。
H21.11.1
フロイトがフランス語の原書からドイツ語に翻訳した著作への訳者序文であるが、催眠と暗示についての独立した主張をなしており、論文といってもいい内容である。
催眠術とその主要な対象疾患であったヒステリーについての考え方において、当時は大きく3つの陣営があったようだ。ひとつは催眠術に懐疑的なグループであり、フロイトの師でもあったマイネルトも「催眠術の問題には依然として『ばかばかしさという後光』がついて回る」と述べていたという。
催眠を支持する者も二つの陣営に分かれていて、ひとつはベルネームを代表とし、催眠に関する現象はすべて暗示によって生じると主張している。もう一方の、シャルコーらのグループの考え方では、催眠状態は身体物理現象であり生理学的現象でもあるということになる。フロイト自身は後者の方の考え方をしているのであるから、その彼がベルネームの著書を翻訳して推奨するのもおかしな感じであるが、催眠術を信じない第一のグループへの啓蒙という意味があるのであろう。
催眠についての理解の仕方は、ヒステリーについての理解にも反映される。ベルネームの立場からは、ヒステリー症状はすべて診察する医師の暗示によって作り出されたものということになってしまう。フロイトの見解では、催眠術によっても医師が患者の症状を自由にすることはできないし、ヒステリー症状には暗示によって作り出すのは不可能な生理学的な要素が含まれているという。
フロイトは、ベルネームが言葉の意味をはっきりさせないままに、すべてを暗示に還元している点を批判している。
そもそも「暗示」とはなにか、これは追求するに値する問いである。たしかにそれは心的な働きかけの一種ではある。これは、ほかの種類の心的な働きかけであるところの、命令、伝達、忠告などとは以下の点において異なっていることを言いたいと思う。つまり暗示においては、なにか二つ目の脳のなかで、その由来が吟味されることなく、あたかもそれが自生的にその脳のなかに生じたかのごとく受け取られるような表象が呼び覚まされる。(1-176)
この「二つ目の脳のなかで」という表現が、後の無意識的な心的過程の理論を、まさに暗示しているようであり、大変興味深い。
さらに、フロイトは暗示を直接暗示と間接暗示に分け、間接暗示の方は「暗示というよりむしろ自己暗示のための刺激である」と述べている。自己暗示は、生理学的な現象であると同時に心的な現象でもあり、それが自生的なヒステリーの症状を作り出す。
入眠についての考え方もおもしろい。目を閉じることは、それが睡眠と強く結びついた随伴現象であるが故に、自己暗示によって睡眠へと導くのだという。
H21.11.9
H・ベルネーム著『暗示とその治療効果』ドイツ語訳第二版への序言
Vorwort zur zweiten deutschen Auflage (1896)
渡邉俊之 訳
初版につけられたフロイトの序文は、第二版ではほんの短い序言に置き換えられてしまった。理由は、その間に催眠の実在性についての著者の主張が広く受け入れられたからだという。しかしそれだけではなく、フロイト自身が自分の考えを、翻訳への序文といった形ではなく、明確に主張できるようになったからというのが大きいのではないか。
短いが、ベルネームへの批判は、よりはっきりと述べられている。
H21.11.9
オーバーシュタイナーによる催眠についての概説的な著作への好意的な書評。人間に「磁性感覚」が備わっているというオーバーシュタイナーの見解と、それに関連してバビンスキーがシャルコーの下で行った実験、というところがどういうものだったのか、興味深い。
H21.11.9
ヒステリー、ヒステロエピレプシー(辞典項目)
Hysterie, Hysteroepilepsie (1888)
渡邉俊之 訳
A・ヴィラーレ編『医学中辞典』の辞典項目として執筆された文章である。他にも、「失語」「脳」「麻痺」「小児麻痺」の項目をフロイトが執筆した可能性があるという。
『ヒステリー研究』出版の8年前の文章であり、辞典項目であるということの性質上からも、一般的で公平な記述になっている。ヒステリー症状の特徴を記述して器質性疾患との違いを述べることに重点が置かれているが、その後の理論を彷彿とするような記述もちらほら見られている。治療についての記述では、ウィアー・ミッチェルの食餌療法を評価しつつも、今後期待がよせられる直接的治療法として、ヨーゼフ・ブロイアーの治療法を紹介している。
H21.11.14
オーギュスト・フォレル著『催眠法』についての論評
Rezension von Auguste Forel, Der Hypnotismus, Stuttgart 1889
渡邉俊之 訳
催眠について書かれたフォレルの著作への好意的な書評である。治療としての催眠を擁護し、催眠に疑いの目を向ける立場、その代表はまたしてもマイネルトなのであるが、に対して辛辣な口調で反論する文章になっている。
フォレルはベルネームに近い考え方で催眠における暗示に重きを置いているが、今回はその点を批判することはなく、ひたすら共同戦線を張っているという感じだ。
H21.11.14
心的治療(心の治療)
Psychische Behandlung (Seelenbehandlung) (1890)
兼本浩祐 訳
初出はR・コスマンとJ・ワイス編の『健康』で、半民間療法的性格を持つ医学領域の記事を集めた一般向けの書籍であったとのこと。ここで言う「心的治療」とは、現代では「心療内科」という時の「心療」に近いものと思われる。時期的にまだ精神分析は生まれていないし、後半はもっぱら催眠療法についての記述となっている。
こういった一般向けの文章を書かせたら、フロイトは天下一品である。豊富な比喩を使った説明で、思わず引き込まれてしまう展開になっている。
前半では、そもそも病の治療というものは心的治療からはじまったという指摘があり、そこで病者は信仰という期待の中で治療者が行使する魔術的な影響によって治癒に導かれたのであった。そういう魔術的治療は、医学の近代化の中で一旦は医師の手を離れたものの、心的治療という合理的な形で再び取り戻されつつある。こうして、後半は催眠療法の話題に導かれていく。
含蓄深く、後の分析理論に結びつくような言及があちらこちらにある。例えば‥‥
狭い意味での情動は、身体過程への特殊な関係をその特徴とするが、厳密に取れば、我々が「思考過程」として通常把握しているあらゆる精神状態は、一定程度は「情動的」であり、そうした思考過程のどれ一つをとっても身体的な表出や身体過程を変化させる能力を必ず伴っているのである。(1-237)
ここで言う「狭い意味での情動」とは、表情や身振りといった形で表現される感情のことであるが、それ以外の思考過程もまた、無意識的な過程を通じて(という表現はここではなされていないが)さまざまな行動へと表出されるのである。こういったテーマは、後に『日常生活の精神病理学』(1901)においてさらに追求されている。
期待という心の状態に対して私たちは多大な興味を抱いているが、それは期待することによって、身体疾患への罹患やそこからの回復に非常に強く影響する多くの心の力が、活性化されうるからである。(1-238)
ここでいう「期待」は、良い期待だけではなく、悪いことへの期待、不安をも含んでいる。当然、良い期待は良い予後へと、悪い期待は悪い予後へと影響を及ぼすことになる。
催眠術を行う者が被催眠者に行使する影響については、次のような重要な考察がなされている。
付け加えて言うならば、被催眠者が催眠術者に対して示すこれほどの軽信性は、催眠以外の実生活においては、愛しい両親に相対している子供でしか見られないものであり、自分の心の生活を催眠と同様の従属性で他人の心の生活に合わせてしまう心のあり方は、全身全霊での献身を伴う恋愛関係の一部においてのみ唯一で、しかし完璧な対応関係があるのみである。唯一の対象を敬い、盲目的にその対象に従うことは、そもそも愛というものの特長の一つである。(1-248)
リビードという言葉こそ使っていないが、まことにフロイトらしい表現である。そして、ここで展開された催眠と暗示についての考察は、30年後の『集団心理学と自我分析』(1921)に引き継がれることになる。
催眠療法に期待をよせる一方で、最後にはその限界について重要な指摘がなされている。催眠による暗示が万能なのであれば、心因性の病気は催眠術にかけて「治りなさい」と暗示することだけで解決してしまうだろう。しかし、そう簡単にはいかない。
暗示の効力は確かに、疾病現象を生じさせそれを維持している力と対抗しはするが、経験上、後者の力は催眠による影響とは比べ物にならないほど大きな次元の力を持っている。(1-254)
これは、精神分析治療における抵抗の話につながっていくところである。そして、本書でも比喩的な説明の中で「抵抗」という表現がすでにみられているのである。
H21.11.19
催眠(辞典項目)
Hypnose (1891)
渡邉俊之 訳
アントン・ブム編『臨床医のための治療辞典』の辞典項目である。催眠療法の実践について、非常に明快に、具体的に書かれている。「一つ一つの暗示はすべてきわめて断固とした態度をもって与えられるべきである(1-267)」という治療原則と、同様の態度で書かれているかのような文章だ。
かといって催眠療法は型にはまった単調なものになってはならず、「医師はたえず、暗示の新しい糸口、自分の力の新しい証明、催眠の進め方の新しい変化などを工夫してゆかなければならない(1-268)」という。
単に暗示を与えるのみでなく、催眠状態の患者に語らせる、ブロイアーのカタルシス療法を示唆するような方法についても書かれている。
H21.11.19
題名は「序言と注解」となっているが、翻訳テキストは序言の部分だけで、注解は次の「注解抜粋」の方にある。前に出版された『神経系の疾患をめぐるサルペトリエール講義』(1886)に続き、フロイトが翻訳し序言と注解を書いている。
序言の中でフロイトは、かつて聴講した者としてシャルコーの講義のすばらしさを賞賛し、その上で臨床神経学におけるフランスとドイツでの姿勢の違いについて指摘している。フランスでは、疾患の病像に重点をおき、典型例を中心とし移行例へと連なる系列の中に個々の症例を捉えようとしている。これに対して、ドイツの流儀では症状同士の関係を生理学的に解釈することに重点がおかれるという。
シャルコーの講義録については、クリストファー・G・ゲッツが編集して英語に翻訳したものがあり、その日本語訳も出版されている。
フランス語の原書は、これかな。
Leons Sur Les Maladies Du Systme Nerveux Faites La Salptrire
題名はフランス語だが、アマゾンの表示では「言語=英語」となっており本当にフランス語かどうか確認できてません。それと、ゲッツの翻訳は手書きで書かれた第一版と印刷された第二版を元に編集された英語版オリジナルなものなので、フランス語版とは異なるでしょう。
他にも、”Jean Martin Charcot”で検索すると、たくさんの講義録などがでてくる。英訳のものが多い。現代においても、シャルコーの講義録は読みつがれているということか。
H21.11.26
シャルコーの講義録のドイツ語訳に訳者のフロイトがつけた注釈から、ヒステリーなど精神医学に関連した部分を抜粋したもの。ここに掲載されていない神経学的な注釈もたくさんあり、それらの多くはシャルコーの見解に批判的なものであったという。尊敬する師のことであっても歯に衣着せずに批判してしまうフロイトってなんだかすごい。
ヒステリー関連の注釈では、ヒステリー発作の中核が外傷の想起であるというフロイト自身の考えを、『ヒステリー研究』(1895)に先立って披露しているところなどがおもしろい。
H21.11.26
講演「催眠と暗示について」についての報告
Bericht über einen Vortrag >Über Hypnose und Suggestion< (1892)
兼本浩祐 訳
フロイトが、1892年の4月27日と5月4日の2回にわたってウィーン医学クラブで行った講演の報告。フロイト自身が書いたものではなく要約もされているので、比喩とユーモアに満ちたいつもの文体は楽しめない。内容的には、『心的治療』などと重なるようだ。
ナンシー学派のベルネームやリエボーに対するフロイト自身の立場は微妙なのか、曖昧な表現になっている。
H21.12.2
『ヒステリー研究』に関連する三篇
Beiträge zu den "Studien über Hysterie" (1892)
芝伸太郎 訳
翌年に出版された「暫定報告」(全体に先立って出版された『ヒステリー研究』の一章)の草稿である。フロイトの草稿は最終的に出版されなかった物以外は残っていないのが通常なので、このように著作と比較できるというのは貴重なことである。共著であったため、共著者ブロイアーに送られた草稿が残ることになったのである。
要点を記したものなので、明快で理解しやすいという利点もある。
H21.12.7
症例「ニーナ・R」についての四つの記録文書
Vier Dokumente über den Fall "Nina R." (1891,1893,1894)
芝伸太郎 訳
スイスのベルビュー保養所に保管されていた、フロイトとブロイアーによる病歴。もちろん出版を目的に書かれたものではない。
ニーナ・Rは1891年の時点で21歳だった女性で、さまざまなヒステリー症状を呈してマリアグリューンのサナトリウムで療養していた際にブロイアーとフロイトによる治療を受けた。催眠による治療はどうもうまくいかなかったようで、患者は退行状態になり、最終的にはスイスのベルビュー保養所に転院となった。その時の紹介状のようなものが本文書である。
病状や治療については断片的な記載になっているが、フロイトやブロイアーが苦心しているところが想像されて興味深い。
H21.12.19
ヒステリー諸現象の心的機制について(講演)
Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene (1893)
芝伸太郎 訳
ウィーン医学クラブにおいて1893年1月11日に行われた講演の記録。「催眠と暗示について」の記録と違って、速記録に演者が手を入れたものであるからほぼ忠実な再現になっているもよう。すでに前半が出版されていたヒステリーの「暫定報告」の内容を大変わかりやすく解説している。「暫定報告」と合わせて読めば理解を助けてくれるだろう。
とりわけ、カタルシス療法について比喩的に述べた次のくだりはすばらしい。
我々の治療は、人間の最も熱烈な欲望の一つ、つまり何かを二回体験できるようにしたいという欲望に沿うものなのであります。誰かが心的外傷を体験したものの、それに対して十分な反応をしませんでした。医者は彼にその同一の心的外傷の二回目の体験をさせますが、それは催眠下においてです。そして、医者はそのとき、彼に対して、完全な反応をするように強要するのです。そうすると彼は、以前には言わば挟みつけられて動きがとれなくなっていた表象を除去します。そのことによって、この表象の作用は消えてしまいます。つまり我々はヒステリーを治癒させるのではなく、終わってはいない反応を完遂させることによって、ヒステリーの個々の症状を治癒させるのです。(1-338)
何かを二回体験できるようにしたいという欲望、というのがおもしろい。『夢解釈』における、「欲望は知覚の繰り返しをめざす」という言及や、後期理論における反復強迫の概念を思い出させる。
H21.12.19
『ヒステリー研究』と同時期に書かれた症例報告である。自分の子供に母乳を与えることが出来ない女性が、催眠による暗示によってきれいに治ってしまった。暗示だけで治ってしまったので、彼女がどのような葛藤を抱き、それがいかにして解消されたかということはわからないままで終わった。その辺りがカタルシス療法によって治療された『ヒステリー研究』の症例と異なり、独立した報告になった理由でもあるのだろう。
しかしそこから引き出されたヒステリー症状理解のためのモデルは、大変示唆に富むものである。
まずフロイトは、「期待の情動と結びついた表象」というものを考える。それには二種類あって、ひとつは「意図」すなわち「私はあれこれのことをするであろう」という表象である。もう一つは「本来の期待」であり、「あれこれのことが私に起こるであろう」という表象である。意図と期待というものをまとめて捉えるというところがおもしろい。そこには、主体性という根本的な違いがあるように見えるが、それもフロイトにかかると相対的なものになってしまうのだろう。
期待というものは、不確実性、すなわち望ましい結果が起こらないかもしれないという恐れを含んでおり、それは「不快な反対表象」の集積として表される。意図に対して不快な反対表象が強くなりすぎると、意志の減退を招き、その代表的な状態が神経衰弱であるという。
これに対してヒステリーでは、不快な反対表象は、意図との関連を外れたところで、身体的な神経支配を通して現実化されてしまう。「意図に反して、吐き気によって授乳ができなくなる」といった具合に。その時点で、不快な反対表象は「対抗意志」として確立されることになる。
神経衰弱における意志力の減退とは対照的に、ヒステリーでは意志の倒錯が生ずるのであり、神経衰弱の諦めを含んだ優柔不断さとは対照的に、ヒステリーでは自分には理解できない内面的な統合不全に対する驚きと怒りが存在するのである。(1-350)
神経衰弱とヒステリーの違いを招く要因について、ここではヒステリーにおける「意識の解離」への傾向とか、神経系の連合鎖における「部分的な疲弊」といったことによって説明が試みられている。
追加の事例として、静かにしないといけない時に舌打ちをしてしまう女性の例があげられ、さらに、中世修道女の神への冒涜と淫猥な言葉に満ちたヒステリー性錯乱、汚言症を伴うチックのことなどに話題は広がっていく。
H22.1.10
本論文は、フロイトのヒステリー研究において特別な意味を持つものであったと思われる。
「器質性運動麻痺とヒステリー性運動麻痺の比較」というテーマは、フロイトがパリのサルペトリエールに留学した際に師シャルコーから与えられていたものだった。フロイトは1888年頃には、論文の大半を書き終えていたらしい。しかし、このフランス語の論文をシャルコーが『神経学アーカイヴ』に掲載したのは、1893年の7月、その突然の死のわずか2週間前のことであったという。
およそ5年間の遅延の理由について、解題の兼本浩祐氏は次のように推測している。
本論文の最初の三節は全くの神経学的著作であり、1886年から遅くとも1888年には完成している。これに対して四節は、「暫定報告」が引用されるとともに、抑圧、浄化反応、恒常性原理などの新たな概念が萌芽的な形で現れている。フロイトがこれらの概念を直接取り扱い始めていたため、それらの概念が自身の中で熟成するのを待って出版を延ばしていた可能性も考えられなくない。
フロイト自身が「偶発的で個人的な理由」とだけしか述べていないのをいろいろ詮索するべきではないのかもしれない。が、私としては「自身の中で熟成するのを待って」というよりも、さらに踏み込んだ推測をしてみたくなる。
ひとつには、フロイトの著作を順に読んでいくと、彼がアイデアを出し惜しみすることはあまりなかったと思われるのだ。ヒステリーについての理論も、『ヒステリー研究』発表の前から既にいろいろな所で書いたり話したりしている。
確かに、四節で展開されるヒステリー症状形成の仮説はシャルコーが敷いた路線から心理学の方向に大きく踏み出している。しかしその内容は、フロイトにとってはすでに目新しいものでもなかった。
そうはいうものの、それをフランス語の論文で師に直接ぶつけていくことには、やはり少々抵抗があったのかもしれない。かといって、三節までの神経学的考察部分だけを提出することにも納得がいかない。そういうジレンマに、彼自身悩んでいたのではなかろうか。
それはともかく、四節の心理学的考察では、ヒステリー性の腕の麻痺を例に、「自我」という概念を引き合いに出して論をすすめている。
心理学的に考察した場合、腕の麻痺は、腕の表象が自我を構成する他の諸概念と連想関係をもつことができない、ということのうちに存する。いま「自我」と述べたが、個人の身体はその大きな一部分を形づくっている。損傷とはそれゆえ、腕の表象が他の観念と連想関係をもつ可能性の廃棄ということになろう。(1-373)
ここの所は、「自我とはとりわけ身体的自我である」という後期の理論を彷彿とさせる。あるいは後期著作のかの言及は、ここに起源があるというべきか。
大脳皮質の損傷による器質性の麻痺では、損傷部分に対応した運動神経支配領域が麻痺に陥る。皮質運動野には、そのような身体支配領域の図式を描くことができる。ヒステリー性麻痺で問題になる身体表象とは、いわば観念レベルにおける身体図式と言えるだろう。
ヒステリー性麻痺において、腕の表象が他の観念との連想関係を絶たれる理由は、それが別のもっと大切な観念と結びつくから、ということらしい。
というのも、ヒステリー性麻痺のすべてのケースにおいて、麻痺した器官や廃棄された機能は、大きな情動的価値を携えた下意識の連想にはめ込まれていることが判明するのであり、この情動的価値が消去されるやいなや腕が自由になることを示すことができるからである。(1-375)
このことを説明するのに、フロイトは3つの示唆に富む比喩をあげている。君主と触れた手を洗おうとしなくなった臣下の笑い話。新郎新婦のために乾杯したグラスを割るという風習。太古の未開部族が、族長の亡骸と共に、生前に使用した物や妻たちまでも葬り去ったこと。つまり、聖なるものと関わりをもったものは、別の用途に用いられることを禁じられるということであろう。
H22.1.28
J・M・シャルコーの死去(1893年8月16日)に際してフロイトから寄せられた追悼文で、『ウィーン医学週報』に掲載された。
臨床医として、研究者として、教育者として、それらを包括する人格として偉大な存在に対して、真摯な賛辞と追悼の意が述べられている。
シャルコーの影響によってヒステリーの研究に乗り出したフロイトは、すでに師の学説を超えたところを歩みつつあった。シャルコーはヒステリーの病因を《神経障害素質血統》という遺伝要因のみに求めていた。フロイトはこのことを批判しつつも、「科学の進歩が、我々の知識を増大させることによって、それまでの知識の多くを無効にしてしまうことは避けがたいことであり、そのこともシャルコーが我々に教えてくれたことである(1-391)」と結んでいる。
H22.2.13
フロイトの神経症理論を構築する基礎概念の多くが、はじめてここで明確に打ち出されている。その中心となるのが、題名ともなっている「防衛」である。
つまり、防衛の能力を有する自我は、相容れない表象を《到来しなかった》表象として取り扱うという課題を自分自身に課す。しかしながら自我はこの課題を直接解決することができない。記憶の痕跡もその表象に付着している情動も、いったんそこに存在してしまうとこれを消し去ることができないからである。(1-397)
ここに示されているように、防衛とは自我の働きである。
それは「相容れない表象」を遠ざけるためになされる。
課せられた課題を自我は直接解決できずに、防衛によってなすのである。
相容れない表象は、大抵の場合に性生活に関するものである。少なくともこの時点でフロイトが経験した症例では、すべてそうであったという。本論文で提示されているケースはみな女性なのだが、こっそりマスターベーションに耽ってしまったとか、ふしだらな性愛的な考えを抱いてしまったといったことである。そういったことが、防衛−精神神経症の病因を形づくる。
どのような防衛がなされるかという、この先の成り行きは、疾患によって異なる。
ヒステリーは、類催眠ヒステリー、防衛ヒステリー(後天性のヒステリー)、鬱滞ヒステリーの三種に分類され、この論文では防衛ヒステリーに限定して話を進めている。『ヒステリー研究』共著者のブロイアーが「類催眠状態」を強調したことなどへの配慮もあったのかもしれない。
ヒステリーでは相容れない表象のその興奮量全体を身体的なものへと移しかえることによってその表象を無害化する。これをわたしは転換と呼ぶことを提案したいと思う。(1-398)
無害化されるといっても、すべてめでたしに終わるわけではなく、むしろ自我は大きな代償を払わされることになる。それが「想い出−象徴」であって、具体的には元の表象と象徴的につながった身体症状や幻覚的感覚である。
次に、恐怖症と強迫表象の場合。
神経症にかかりやすい人に、転換の適性はないけれども、耐えがたい表象を防衛する適性があって、こういった表象を情動から引き離そうとすることが行われる場合、このような情動は心的領域にとどまるにちがいない。こうして弱体化された表象はすべての連想から切り離されて意識のなかに残る。しかしその表象から自由になった情動は、それ自体は相容れなくはないほかの表象と結びつく。これらの表象がこういった「誤った結合」を通じて強迫表象となるのである。(1-400)
こちらの防衛は、「情動からの表象の分離とその情動の誤った結合」あるいは「情動の配転」と呼ばれる。また、後には「遷移」と呼ばれることになる過程である。
「ある種の幻覚性精神病」における防衛は、次のようになる。
この防衛の本質はすなわち、自我がその耐えがたい表象をその情動ともども棄却してしまい、自我はあたかもそのような表象が自我のなかに一度たりとも入り込んではいなかったかのように振舞おうという点に存する。ただし、これが成功した時点で、この人物はおそらく「幻覚性錯乱」としか分類できない精神病の状態になるだろう。(1-408)
この防衛は「精神病への逃避」と呼ばれる。そのまんまという感じだが。
さて、自我が直接的に解決するのではなしに用いる防衛とは、いかなる過程なのだろうか。それは、「意識が関与せずに生じる過程である(1-402)」という。それは、「心的な性格をもつ過程ではまったくなく、物理的な過程(1-402)」であるという。
後のフロイトであれば、ずばり「無意識的な過程である」と表現するところであろう。
ちなみに、後に重要な術語となる「抑圧」という言葉もこの論文にすでに見られるが、まだ特別な概念として強調されているわけではない。
最後に、後の経済論的観点、恒常性原則、リビード理論などの萌芽ともいえる記述がみられる。それは、「補助表象」として言及されている。
それは――わたしたちはこれを測定する手段をもたないのだが――心的な諸機能について量としてのあらゆる特徴を有するなんらかのもの(情動総計、興奮量全体)が区別されるべきであるという表象である。それは、増量したり、減量したり、遷移したり、放散したりすることができ、表象の記憶痕跡のなかにまで広がり、いうなれば身体表面に広がっている電荷のようなものである。(1-410)
まとめると、本論文は防衛という概念を中心にした神経症病理のモデルを提示しており、そこには後に精神分析理論に発展する要素が多く含くまれている。
H22.3.1
前の論文にひきつづき、本論文もフロイト理論の発展において大変重要な意味をもつ。
まず、「不安神経症」という現在にも続いている疾患概念が、ここで初めて提示された。そして、その中心となる情動として、「不安」が正面からとりあげられた。
少々意外なことではあるが、不安と不安神経症について大々的に論じられることはその後久しくなく、後期の論文『制止・症状・不安』(1926)を待たねばならない。ちなみに『制止・症状・不安』では、不安について本論文で提示された仮説が根本的に変更され、さらに『防衛−神経精神症』のテーマとなっていた「防衛」という概念が復活したのであった。
不安というものは、それほどフロイトにとって困難なテーマであったらしい。本論文によれば、不安神経症における不安は「抑圧された観念に由来しておらず、心理学的分析においてはそれ以上には還元不能であり、精神療法では対抗することができない(1-421)」のだという。この時点では「精神分析」という言葉はまだ使われないが、要するに分析的技法によって解明されることも治療されることもできないということになる。
本論文では、不安神経症の症状を記述し、患者への問診からその病因を推測するという方法で考察をすすめている。症状記述においては、「何か悪いことが起こりそうだ」という不安な予期を慢性的不安の中核症状としてあげている。そしてそれをベースに起こる不安発作を、その際に起こる身体症状に注目して記述している。身体症状としては、動悸、呼吸困難、発汗、振戦、食欲亢進、下痢、めまい、うっ血、感覚異常をあげている。
不安神経症の問診によって明らかになった重要な要因は、男性においても女性においても「性生活に由来するさまざまの有害事象や影響(1-424)」であったという。有害事象の中でも特にフロイトが重視していたのは、体外射精である。
以上のような検討の結果導かれた仮説は、以下のようなものであった。
すなわち、不安神経症の機制は、心の領域から身体的な性的興奮が逸らされてしまい、その結果、この興奮が異常な形で利用されることのうちに求められるべきであるという推察がそれである。(1-434)
本論文では、「リビード」という言葉が初めて登場し、キーワードとして繰り返し使われている。ただしこの時点でそれは、心的過程として意識されうる性欲の量を表しており、後のように無意識的なものをも含む概念ではない。そもそもまだ「無意識的」という概念がないので、リビードの元になるものは単に「身体的な興奮」と呼ばれている。
もう一つ、不安の本質に関連した重要な概念として登場するのが、「投影」である。
内因性に出現する(性的な)興奮を相殺することができない場合、精神はこの興奮を外部に向けて投影するかのように振舞うのである。(1-439)
内的な危機に際してそれに十分対応できない心的装置が、それを外部から来るものとみなして防衛しようとするというのは、この後もフロイトがしばしば採用する基本的な考え方の一つである。
最後に、不安神経症と他の神経症との関係、およびその混合について述べられる。
不安神経症と神経衰弱は、共に「興奮の源泉や障害の誘因が身体領域にある(1-441)」という点で共通しており、それらが心的領域にあるヒステリーや強迫神経症とは対極にある。一方、不安神経症と神経衰弱は、興奮の集積(不安神経症)と貧困化(神経衰弱)という方向での対極をなしている。これらがさまざまな割合で混合しておこることも多く、混合神経症とみなされる。
H22.3.18
強迫と恐怖症、その心的機制と病因
Obsessions et Phobies. Leur méchanisme psychique et leur étiologie (1895)
立木康介 訳
フランス語で書かれた論文。強迫と恐怖症、そして不安神経症の関係を簡潔にまとめている。強迫の観察例を11例(事例群を含むので事例数としてはもっと多い)提示しており、全体としてコンパクトで読みやすい論文になっている。
広い意味の強迫は、真性の強迫と恐怖症に区別される。それらは共に、「一、患者を圧倒する観念、二、それに結合された情緒状態(1-446)」という要素を持つ。
恐怖症では、情緒状態は常に不安である。真性の強迫では、それは疑い、後悔、怒りといった他の情緒状態でもあり得る。
強迫観念とは、代理物である。それは、情緒状態にもともと結びついていた正当な観念が、置き換えられたものである。置き換えは、「相容れない観念にたいする自我の防衛行為(1-453)」である。そのような置き換えは、特殊な心的素因の表現でもあるようだ。(ここでもフロイトは、神経症の病因として素因を強調している。それは、心理学的解釈と両立するものなのだ。)
恐怖症は代理物ではない。そもそも代理されるような観念が存在しない。それは、対象を持たない不安という情緒状態が、対象を得たものである。不安は、心的機制を介さずに、直接的に性的な起源から生じるものである。恐怖症は、不安神経症の一部をなしている。
H22.4.1